読み終えた本「素数ゼミの謎」 ― 2016年07月25日
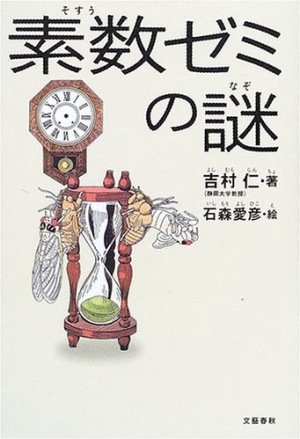
読み終えた本「素数ゼミの謎」吉村 仁著 文藝春秋
米国には13年(4種)と17年(3種)毎に大発生するセミが知られている。
このセミが,なぜ「素数」の発生周期を持つかを,数学的に説明した。
吉村以前に,素数年による周期発生の意味として,捕食者との同期を避けるためと言われていたが,吉村は,氷河期がセミの生息範囲を狭め,近親交配を繰り返す結果,周期がわずかに違う交雑種が生まれていくとした。そうすると,ずれた時期に発生した個体は交配する相手がいないため,これが積み重なると,種の滅亡へとつながる。そこで,13と17という素数の発生年が,必要最小の交雑を防ぐ数だったのではというものです。この2数の最小公倍数は素数同士なので221年となる。
しかし,疑問も残る。13年ゼミと17年ゼミが交雑して15年ゼミができるのかということが確認されていない。米国には周期ゼミ以外に100種ものセミが生息しているが,それらは素数の発生周期ではなくても,種を存続させている。
これは私見だが,偶然(というか,当初はそれなりの生態学的な,そして数学的な意味があり),素数の発生年を持ってしまったため,もうそこから這い出ることのできない穴にはまってしまったセミなのではないかと思うのです。
少し考えてみました。
北米以外に周期ゼミがいない理由。これは吉村先生のいう通り,氷河期のためで,発生周期が13年以上と長くなった。日本のセミは毎年発生するが,1933年,東北大学の佐藤隼夫さんが仙台の大学構内で,金網で囲った飼育室を作り,アブラゼミとミンミンゼミを多数放した。そうしたところ,7年目にアブラゼミとミンミンゼミの成虫がそれぞれ見つかった。アロエでツクツクボウシを飼育した例では,翌年に成虫が出てきたそうで,発生の周期は条件によって様々なようだ。
*「月刊たくさんのふしぎ:宮武頼夫著」福音館書店1987年
*日本で周期ゼミが発生しないのは,氷河期がなかったから,素数年の発生がなかったためだろう。
参考:
http://wired.jp/2009/05/25/13年か17年で大発生するセミ:謎を日本の研究者ら/
17年ゼミの発生の様子
https://www.youtube.com/watch?v=rXlIeUmqrpk
米国には13年(4種)と17年(3種)毎に大発生するセミが知られている。
このセミが,なぜ「素数」の発生周期を持つかを,数学的に説明した。
吉村以前に,素数年による周期発生の意味として,捕食者との同期を避けるためと言われていたが,吉村は,氷河期がセミの生息範囲を狭め,近親交配を繰り返す結果,周期がわずかに違う交雑種が生まれていくとした。そうすると,ずれた時期に発生した個体は交配する相手がいないため,これが積み重なると,種の滅亡へとつながる。そこで,13と17という素数の発生年が,必要最小の交雑を防ぐ数だったのではというものです。この2数の最小公倍数は素数同士なので221年となる。
しかし,疑問も残る。13年ゼミと17年ゼミが交雑して15年ゼミができるのかということが確認されていない。米国には周期ゼミ以外に100種ものセミが生息しているが,それらは素数の発生周期ではなくても,種を存続させている。
これは私見だが,偶然(というか,当初はそれなりの生態学的な,そして数学的な意味があり),素数の発生年を持ってしまったため,もうそこから這い出ることのできない穴にはまってしまったセミなのではないかと思うのです。
少し考えてみました。
北米以外に周期ゼミがいない理由。これは吉村先生のいう通り,氷河期のためで,発生周期が13年以上と長くなった。日本のセミは毎年発生するが,1933年,東北大学の佐藤隼夫さんが仙台の大学構内で,金網で囲った飼育室を作り,アブラゼミとミンミンゼミを多数放した。そうしたところ,7年目にアブラゼミとミンミンゼミの成虫がそれぞれ見つかった。アロエでツクツクボウシを飼育した例では,翌年に成虫が出てきたそうで,発生の周期は条件によって様々なようだ。
*「月刊たくさんのふしぎ:宮武頼夫著」福音館書店1987年
*日本で周期ゼミが発生しないのは,氷河期がなかったから,素数年の発生がなかったためだろう。
参考:
http://wired.jp/2009/05/25/13年か17年で大発生するセミ:謎を日本の研究者ら/
17年ゼミの発生の様子
https://www.youtube.com/watch?v=rXlIeUmqrpk

最近のコメント