読み終えた本「武士道」 ― 2016年05月09日

読み終えた本「武士道」
新渡戸稲造著 大久保秀樹訳 角川ソフィア文庫(H27.5.25)
あまりに有名で説明は必要ないと思いますが,新訳が出たのでそれを図書館から借りました。
著者は文久二年の生まれで,武士の三男だった。幼くして英語を学び,札幌農学校の同期生に内村鑑三がいる。
同じ年生まれに,森鴎外,岡倉天心がおり,共に西欧に留学・遊学している。そんな時代だ。
ジョンズ・ホプキンス大学に学び,同期生には後の大統領となるウィルソンがいる。
フィラデルフィアのクエーカー教徒の娘,メアリーと恋仲になり,苦労の末結婚した。
こういう背景から,自らのアイデンティーを模索することになったのだろう。
武士道と騎士道との比較,日本独自の倫理観,価値観をいかに西欧人に理解してもらうか,その努力がこの著書となったのか。
以下,メモ
武士道と騎士道はほぼ同等のもので「ノブレス・オブリージュ:高貴な身分に伴う義務」であるが、その国特有に発展したものなので、あえて「bushido」と表記するのだと説明している。
「勇気と平静」で、昔の戦は、詩歌のやり取りもある、スポーツ的な要素もある、という例に、我がご先祖の話が引き合いに出されていた。
「衣川の合戦で、総崩れになった東軍の大将・安倍貞任は敗走しようとした時、これを追った源義家は貞任に「敵に後ろを見せるとは武士の恥」と大声で呼びかけると、貞任は馬を止めた。すかさず義家「衣のたてはほころびにけり」と下の句を詠むと貞任うろたえることなく「年を経し糸の乱れの苦しさに」と上の句を返した。これを聞いた義家は、貞任めがけて引きしぼっていた弓を緩め、敵将を逃した。」と述べ,戦場での平静・平常心を説明する。
「礼とは、敬虔な思いを込めて、こう言うことができるだろう、---長く耐え忍び、親切にし、妬まず、驕らず、ふくれず、無作法にふるまわず、欲張らず、怒らず、邪心を抱かないことだと。---」
外国人宣教師夫人が奇異に感じたこと。日傘を持たずに外出した時、日傘を持った日本人男性と出会って立ち話をしたが、彼はすぐに帽子を脱いで挨拶を交わした後、日傘を畳み陽射しの中に居た。新渡戸は、これは「他人への共感」だと説明する。
贈り物に関して西洋では、「良い品物だからあなたに差し上げる」だが、日本では「あなたは素晴らしい方なので相応しい品物など無いが、粗末なものではあるが受け取ってほしい」と云う。どちらも同じ事を言っているのだが、西洋は贈る品物自体を言っており、日本では贈り物をする気持ちを言っている。
カーライルの「恥はすべての徳,すべての良きふるまいと道徳を生み出す土壌である。」と同じことを,カーライルに先立つこと数世紀前に孟子が同じことを言っている。
しかし、新渡戸は、武士は名誉を重んじたが,背中にノミが飛んでいると注意してくれた町人をその場で切り捨てたというような,武士の行き過ぎた名誉心を紹介し,批判している。
人から謗られても,誹り返してはならない。そうすれば更なる高みに向かうと朱子学や陽明学の教えを紹介している。
(*武士は言い訳をしないということか。この話を思い出してしまう。ミュージシャン・細野晴臣の祖父,細野正文は鉄道員在外研究員としてのロシア留学の帰途,タイタニック号に乗り合わせた。沈没の際に他人を押しのけて救命ボートに乗ったと白人の一人に証言されたという、実は誤報が帰国後伝えられ,日本中から批判された。そのために名誉と地位を失ったが,生涯弁明しなかったという。)
切腹と仇討ち
切腹については、幕末から明治維新にかけて来日したイギリス外交官・ミットフォードの著書「昔の日本の物語」の中で、切腹に立ち会った時の描写をそのまま引用している。
これは、「神戸事件」の責任者として滝善三郎が切腹したものであるが、神戸事件には英国公使のパークスが居合わせており、外交問題に発展したのである。英文で紹介された切腹の凄まじい、しかし厳粛な様子が、世界にセンセーションを巻き起こすこととなった。
刀・侍の魂
暗殺者と幾度も対峙した勝海舟の「俺は一度も人を切ったことが無い」という言葉を引いて、抜かざる刀こそ、伝家の宝刀であることを説明している。
西洋のバラに対して、日本人の大和心をサクラに例えた。
「欧米流のキリスト教ー元来の創始者の慈悲や清らかさよりはアングロサクソン流の気まぐれや空想の入ったーは武士道という幹に接ぎ木するには貧弱な若枝である。」
*現代になっても,日本人の中には,「武士道」が形を変えて残っている。そのように意識したい。
新渡戸稲造著 大久保秀樹訳 角川ソフィア文庫(H27.5.25)
あまりに有名で説明は必要ないと思いますが,新訳が出たのでそれを図書館から借りました。
著者は文久二年の生まれで,武士の三男だった。幼くして英語を学び,札幌農学校の同期生に内村鑑三がいる。
同じ年生まれに,森鴎外,岡倉天心がおり,共に西欧に留学・遊学している。そんな時代だ。
ジョンズ・ホプキンス大学に学び,同期生には後の大統領となるウィルソンがいる。
フィラデルフィアのクエーカー教徒の娘,メアリーと恋仲になり,苦労の末結婚した。
こういう背景から,自らのアイデンティーを模索することになったのだろう。
武士道と騎士道との比較,日本独自の倫理観,価値観をいかに西欧人に理解してもらうか,その努力がこの著書となったのか。
以下,メモ
武士道と騎士道はほぼ同等のもので「ノブレス・オブリージュ:高貴な身分に伴う義務」であるが、その国特有に発展したものなので、あえて「bushido」と表記するのだと説明している。
「勇気と平静」で、昔の戦は、詩歌のやり取りもある、スポーツ的な要素もある、という例に、我がご先祖の話が引き合いに出されていた。
「衣川の合戦で、総崩れになった東軍の大将・安倍貞任は敗走しようとした時、これを追った源義家は貞任に「敵に後ろを見せるとは武士の恥」と大声で呼びかけると、貞任は馬を止めた。すかさず義家「衣のたてはほころびにけり」と下の句を詠むと貞任うろたえることなく「年を経し糸の乱れの苦しさに」と上の句を返した。これを聞いた義家は、貞任めがけて引きしぼっていた弓を緩め、敵将を逃した。」と述べ,戦場での平静・平常心を説明する。
「礼とは、敬虔な思いを込めて、こう言うことができるだろう、---長く耐え忍び、親切にし、妬まず、驕らず、ふくれず、無作法にふるまわず、欲張らず、怒らず、邪心を抱かないことだと。---」
外国人宣教師夫人が奇異に感じたこと。日傘を持たずに外出した時、日傘を持った日本人男性と出会って立ち話をしたが、彼はすぐに帽子を脱いで挨拶を交わした後、日傘を畳み陽射しの中に居た。新渡戸は、これは「他人への共感」だと説明する。
贈り物に関して西洋では、「良い品物だからあなたに差し上げる」だが、日本では「あなたは素晴らしい方なので相応しい品物など無いが、粗末なものではあるが受け取ってほしい」と云う。どちらも同じ事を言っているのだが、西洋は贈る品物自体を言っており、日本では贈り物をする気持ちを言っている。
カーライルの「恥はすべての徳,すべての良きふるまいと道徳を生み出す土壌である。」と同じことを,カーライルに先立つこと数世紀前に孟子が同じことを言っている。
しかし、新渡戸は、武士は名誉を重んじたが,背中にノミが飛んでいると注意してくれた町人をその場で切り捨てたというような,武士の行き過ぎた名誉心を紹介し,批判している。
人から謗られても,誹り返してはならない。そうすれば更なる高みに向かうと朱子学や陽明学の教えを紹介している。
(*武士は言い訳をしないということか。この話を思い出してしまう。ミュージシャン・細野晴臣の祖父,細野正文は鉄道員在外研究員としてのロシア留学の帰途,タイタニック号に乗り合わせた。沈没の際に他人を押しのけて救命ボートに乗ったと白人の一人に証言されたという、実は誤報が帰国後伝えられ,日本中から批判された。そのために名誉と地位を失ったが,生涯弁明しなかったという。)
切腹と仇討ち
切腹については、幕末から明治維新にかけて来日したイギリス外交官・ミットフォードの著書「昔の日本の物語」の中で、切腹に立ち会った時の描写をそのまま引用している。
これは、「神戸事件」の責任者として滝善三郎が切腹したものであるが、神戸事件には英国公使のパークスが居合わせており、外交問題に発展したのである。英文で紹介された切腹の凄まじい、しかし厳粛な様子が、世界にセンセーションを巻き起こすこととなった。
刀・侍の魂
暗殺者と幾度も対峙した勝海舟の「俺は一度も人を切ったことが無い」という言葉を引いて、抜かざる刀こそ、伝家の宝刀であることを説明している。
西洋のバラに対して、日本人の大和心をサクラに例えた。
「欧米流のキリスト教ー元来の創始者の慈悲や清らかさよりはアングロサクソン流の気まぐれや空想の入ったーは武士道という幹に接ぎ木するには貧弱な若枝である。」
*現代になっても,日本人の中には,「武士道」が形を変えて残っている。そのように意識したい。
伊藤マンショ ― 2016年04月26日

国立博物館で,2014年にイタリア・北部で発見された天正遣欧少年使節の一人,伊藤マンショの肖像画が展示されるそうです。
今まで知られていた絵では,稚拙すぎてリアリティーがありませんでしたが,ティントレットの息子が完成させた絵ですので,本当にはっとさせられます。実物を見てみたくなりました。
そもそも,4人の肖像画をティントレット(生前だった)に依頼したことも知らなかった。
「クアトロ・ラガッツィ-天正少年使節と世界帝国」
若桑 みどり (著) 集英社 (2003/10/24)
を読んだのは12年も前だったので,この件が書かれていたのかどうかも記憶が定かでない。手元にあるので,読み直してみたくなった。
*ローマの教皇庁は,この4人の「公子」達をうまく利用しようとし,法王に謁見させるのは「東方の三賢者」になぞらえて3名にしたかったため,一人を無理やり病欠(健康だったのに)させてしまうということもやっている。このあたりのことは著者の若桑氏がヴァチカンに保管されているイエズス会の文書を読み解いたものらしく,非常に興味深い内容だった。
今まで知られていた絵では,稚拙すぎてリアリティーがありませんでしたが,ティントレットの息子が完成させた絵ですので,本当にはっとさせられます。実物を見てみたくなりました。
そもそも,4人の肖像画をティントレット(生前だった)に依頼したことも知らなかった。
「クアトロ・ラガッツィ-天正少年使節と世界帝国」
若桑 みどり (著) 集英社 (2003/10/24)
を読んだのは12年も前だったので,この件が書かれていたのかどうかも記憶が定かでない。手元にあるので,読み直してみたくなった。
*ローマの教皇庁は,この4人の「公子」達をうまく利用しようとし,法王に謁見させるのは「東方の三賢者」になぞらえて3名にしたかったため,一人を無理やり病欠(健康だったのに)させてしまうということもやっている。このあたりのことは著者の若桑氏がヴァチカンに保管されているイエズス会の文書を読み解いたものらしく,非常に興味深い内容だった。
読み終えた本「或る少女の死まで」 ― 2016年02月27日
読み終えた本
或る少女の死まで 室生犀星
書評だったか何だったか、文章が美しいというので、今まで室生犀星は読んだことがなかったので、青空文庫からダウンロードした。
ある貧乏詩人と隣りの九歳の少女ふじ子、そして筆者が友人らと傷害事件を起こすことになる飲み屋で酌婦をしている少女への思い。
一方は何不自由ない境遇、もう一方はいかにも病弱そうで、仕事中に居眠りするのが幸せそうなと、対照的に描く。
しかし、ふじ子は帰郷先の九州で、急病で亡くなったと手紙を受け取る。実際にあったことなのか、あっけない結末。
時代は母の生まれた年(明治44年)。当時の世相を窺い知る。
このように、「少女」を中心に置く小説の手法は、ステレオタイプのようでもある。例えば、鴎外の「舞姫」「うたかたの記」や、芥川の「南京の基督」にも見られるように思う。ふと、そんな事を思った。
或る少女の死まで 室生犀星
書評だったか何だったか、文章が美しいというので、今まで室生犀星は読んだことがなかったので、青空文庫からダウンロードした。
ある貧乏詩人と隣りの九歳の少女ふじ子、そして筆者が友人らと傷害事件を起こすことになる飲み屋で酌婦をしている少女への思い。
一方は何不自由ない境遇、もう一方はいかにも病弱そうで、仕事中に居眠りするのが幸せそうなと、対照的に描く。
しかし、ふじ子は帰郷先の九州で、急病で亡くなったと手紙を受け取る。実際にあったことなのか、あっけない結末。
時代は母の生まれた年(明治44年)。当時の世相を窺い知る。
このように、「少女」を中心に置く小説の手法は、ステレオタイプのようでもある。例えば、鴎外の「舞姫」「うたかたの記」や、芥川の「南京の基督」にも見られるように思う。ふと、そんな事を思った。
薔薇の名前 ― 2016年02月21日
ウンベルト・エーコが亡くなったというニュース。「どこかで聞いたことが・・」続いてニュースは「薔薇の名前の作者で・・」あ,そうだったのか。
映画は確かに観たが難解で,結局なんの話なのかさっぱり分からなかった。
夜中に手洗いに立ったら目が冴えてきたので,気になった「薔薇の名前」関連をiPad片手に寝床で検索を始めた。
エーコという人は,調べてみると大変な人で,この小説は彼の研究成果を,読者に分かりやすく,親しみやすいようにと,登場人物の名前には,色々と連想させるような設定をしている。
バスカーヴィルのウィリアムは,「シャーロック・ホームズ」と「オッカムのウィリアム」を連想させるようにしており,盲目の修道士ホルヘ・ダ・ブルゴスも「ホルヘ・ルイス・ボルヘスはアルゼンチンの国立図書館の館長で、盲目となった人物:Wikipedia」を連想させるようにしているらしい。
小説の舞台はオッカムのウィリアムの時代なので14世紀。そんな時代のキリスト教での「普遍論争」での異端審問が中心にある。普遍論争というのは,実在論と唯名論との争いで,個物が先か,普遍が先か,というような哲学上・神学上の争いのことのようだ。だから小説の「薔薇の名前」にも謎が秘められている。
オッカムのウィリアムは,「オッカムの剃刀」を掲げて,急進的な唯名論の立場に立ったため,ローマ教皇から異端審問にかけられそうになり,神聖ローマ皇帝の元へ逃亡する。
オッカムの剃刀は,「説明に不要な存在を切り落とすことの比喩」だそうで,「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とうことだ。
分子のように目に見えもしないもので何かを説明するのは,この考えに反すると,エルンスト・マッハがボルツマンを攻撃したことが,ボルツマンの自殺につながるという説もあるくらいのものだそうだ。
エーコに戻るが,エーコは5万冊もの蔵書を持つ知の巨人であり,彼の研究は中世のキリスト教や哲学,記号論に及んでおり,それらの基礎知識が全くない者には,小説が難解なのは仕方のないことかもしれない。
しかし,エーコのような人は「キリスト教世界」からしか生まれないように思うのは早計だろうか。イスラム世界でのどのような研究がなされているのだろうか。かつてはイスラム世界の方が,閉鎖的なキリスト教世界よりもずっと科学や天文学が発達していた時代もあった。では,近現代ではどうなのだろうか。
と,そんなことを考えていたら,急に腹が減ってきた。血中のブドウ糖を使い切ってしまったようだ。で,また寝ることにした。すぐに寝てしまったようだ。(^_^;)
映画は確かに観たが難解で,結局なんの話なのかさっぱり分からなかった。
夜中に手洗いに立ったら目が冴えてきたので,気になった「薔薇の名前」関連をiPad片手に寝床で検索を始めた。
エーコという人は,調べてみると大変な人で,この小説は彼の研究成果を,読者に分かりやすく,親しみやすいようにと,登場人物の名前には,色々と連想させるような設定をしている。
バスカーヴィルのウィリアムは,「シャーロック・ホームズ」と「オッカムのウィリアム」を連想させるようにしており,盲目の修道士ホルヘ・ダ・ブルゴスも「ホルヘ・ルイス・ボルヘスはアルゼンチンの国立図書館の館長で、盲目となった人物:Wikipedia」を連想させるようにしているらしい。
小説の舞台はオッカムのウィリアムの時代なので14世紀。そんな時代のキリスト教での「普遍論争」での異端審問が中心にある。普遍論争というのは,実在論と唯名論との争いで,個物が先か,普遍が先か,というような哲学上・神学上の争いのことのようだ。だから小説の「薔薇の名前」にも謎が秘められている。
オッカムのウィリアムは,「オッカムの剃刀」を掲げて,急進的な唯名論の立場に立ったため,ローマ教皇から異端審問にかけられそうになり,神聖ローマ皇帝の元へ逃亡する。
オッカムの剃刀は,「説明に不要な存在を切り落とすことの比喩」だそうで,「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とうことだ。
分子のように目に見えもしないもので何かを説明するのは,この考えに反すると,エルンスト・マッハがボルツマンを攻撃したことが,ボルツマンの自殺につながるという説もあるくらいのものだそうだ。
エーコに戻るが,エーコは5万冊もの蔵書を持つ知の巨人であり,彼の研究は中世のキリスト教や哲学,記号論に及んでおり,それらの基礎知識が全くない者には,小説が難解なのは仕方のないことかもしれない。
しかし,エーコのような人は「キリスト教世界」からしか生まれないように思うのは早計だろうか。イスラム世界でのどのような研究がなされているのだろうか。かつてはイスラム世界の方が,閉鎖的なキリスト教世界よりもずっと科学や天文学が発達していた時代もあった。では,近現代ではどうなのだろうか。
と,そんなことを考えていたら,急に腹が減ってきた。血中のブドウ糖を使い切ってしまったようだ。で,また寝ることにした。すぐに寝てしまったようだ。(^_^;)
読み終えた本「第四の大陸」 ― 2016年02月02日
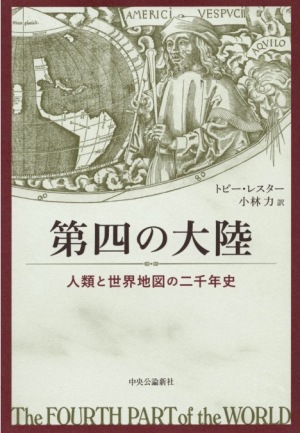
読み終えた本「第四の大陸」
トビー・レスター (著), 小林 力 (翻訳)
中央公論新社 (2015/8/6)
内容紹介
500年前に1000部印刷され、後生に残されたのはただ1部。 その驚くべき地図〈ヴァルトゼーミュラー世界図〉を 米国議会図書館は2003年、1000万ドルという途方もない額で買い取った。 「アメリカの出生証明書」であるとして-- 古代ギリシャ、中世、ルネサンス、そして大航海時代へ。 未知の大地に思いを馳せた人々の世界観どのように変遷してきたのか。 新世界を初めて「アメリカ」と命名した驚くべき地図 〈ヴァルトゼーミュラー世界図〉誕生まで 地図製作技術の発展をめぐる壮大な歴史の万華鏡。 【ヴァルトゼーミュラー世界図ほか貴重な古典地図、 図版多数収録。カラー口絵8ページ】
メモ
欧州人が居ると信じていた東方の大王「プレスター・ジョン」と、モンゴル帝国の大ハーンを同一視するような過程がおもしろい。
時は、失敗に終わった第七次十字軍遠征のあと。モンゴルはキリスト教に改宗しそうだという、ありもしない噂が広まる。フビライ・ハーンの時に、伝聞ではあるが、マルコ・ポーロの「東方見聞録」が広まる。フビライはそれまでのハーンと違い、慈悲深かった。
モンゴル帝国の首都は今の北京で、失われた理想の都は「上都:シャンドウ:つまりザナドゥ」といった。
ペトラルカは、修道院などに埋もれていた古典を発掘し、ラテン語に翻訳した。ローマの崩壊後、古代の英知と知識が失われたことを嘆き、それらに無関心だった知識人に対して怒りを露わにしている。
天文学者としてのプトレマイオスしか知らなかったが、地理学者、地図製作学者としても業績が高い。エジプト出身だが、マケドニアの名門の出で、ローマ人だった。地図の投影法を考案した。古代ギリシャ人は、既に世界が球体であることを知っていた。
ペトラルカやボッカッチョなどの人文主義運動が、ギリシャ語で書かれた古典を掘り起こした。ローマが東西に分裂したことにより、ローマはラテン語を、ビザンツ帝国はギリシャ語を重視するようになったため、ギリシャ語の古典が顧みられなかったことによる。この動きが後のルネサンスにつながっていく。
後は面倒になってメモなし。(^_^;)
世界がどうなっているか,世界地図,地球儀の歴史。アメリカがいつからアメリカと呼ばれるようになったのか,アメリカはよほど知りたかったようです。
トビー・レスター (著), 小林 力 (翻訳)
中央公論新社 (2015/8/6)
内容紹介
500年前に1000部印刷され、後生に残されたのはただ1部。 その驚くべき地図〈ヴァルトゼーミュラー世界図〉を 米国議会図書館は2003年、1000万ドルという途方もない額で買い取った。 「アメリカの出生証明書」であるとして-- 古代ギリシャ、中世、ルネサンス、そして大航海時代へ。 未知の大地に思いを馳せた人々の世界観どのように変遷してきたのか。 新世界を初めて「アメリカ」と命名した驚くべき地図 〈ヴァルトゼーミュラー世界図〉誕生まで 地図製作技術の発展をめぐる壮大な歴史の万華鏡。 【ヴァルトゼーミュラー世界図ほか貴重な古典地図、 図版多数収録。カラー口絵8ページ】
メモ
欧州人が居ると信じていた東方の大王「プレスター・ジョン」と、モンゴル帝国の大ハーンを同一視するような過程がおもしろい。
時は、失敗に終わった第七次十字軍遠征のあと。モンゴルはキリスト教に改宗しそうだという、ありもしない噂が広まる。フビライ・ハーンの時に、伝聞ではあるが、マルコ・ポーロの「東方見聞録」が広まる。フビライはそれまでのハーンと違い、慈悲深かった。
モンゴル帝国の首都は今の北京で、失われた理想の都は「上都:シャンドウ:つまりザナドゥ」といった。
ペトラルカは、修道院などに埋もれていた古典を発掘し、ラテン語に翻訳した。ローマの崩壊後、古代の英知と知識が失われたことを嘆き、それらに無関心だった知識人に対して怒りを露わにしている。
天文学者としてのプトレマイオスしか知らなかったが、地理学者、地図製作学者としても業績が高い。エジプト出身だが、マケドニアの名門の出で、ローマ人だった。地図の投影法を考案した。古代ギリシャ人は、既に世界が球体であることを知っていた。
ペトラルカやボッカッチョなどの人文主義運動が、ギリシャ語で書かれた古典を掘り起こした。ローマが東西に分裂したことにより、ローマはラテン語を、ビザンツ帝国はギリシャ語を重視するようになったため、ギリシャ語の古典が顧みられなかったことによる。この動きが後のルネサンスにつながっていく。
後は面倒になってメモなし。(^_^;)
世界がどうなっているか,世界地図,地球儀の歴史。アメリカがいつからアメリカと呼ばれるようになったのか,アメリカはよほど知りたかったようです。
読み終えた本「ニッポン日記」マーク・ゲイン著 ― 2015年12月07日

読むのに時間がかかった。終戦後の日本を米国の記者が日記にしている。非常に興味があった。
ニッポン日記
マーク・ゲイン著 筑摩叢書12 筑摩書房 1963年
1945年12月に厚木飛行場に降り立ち、その後一年余り日本に滞在した、主としてシカゴ・サン紙に記事を書き送った記者が、占領時日本の体験を日記としてまとめたもの。
講和条約発効前に翻訳出版された。この本によると,米国はこれほどあっさり日本が全面降伏するとは思っていなかったようで,占領政策も憲法も急ごしらえ。さらに日本の政府はしたたかで,占領軍が進駐してくる前に,様々な策略を講じて戦犯にされそうな人員を配置しなおし,財閥の財産は見事に分散させ,大量の軍の物資は隠匿した。日本はわずかの期間に準備を整えてから占領軍を迎えた。翻弄されたのはむしろ占領軍だった。占領軍内部での政策の不一致や内部対立があり,日本政府はGHQの命令にもサボタージュで応戦するしで,ほとほと手を焼いたようだ。占領軍よりも既存の日本政府の情報網・指令系統の方が完璧で,ことごとく裏を書かれたことが随所にみられる。この本が戦後ほとんど顧みられていないのは残念。
日本の戦後は,GHQによって解放された左翼活動家が,かえってGHQの思惑とは別な方向へ進んでいくのを,GHQ自身が戸惑いながら押さえつけていたことがよくわかる。
筆者はGHQのやり方には常に批判的で,当局からはかなり睨まれていたようだ。
筆者の本名はモウ・ギンズバーグといい,亡命ユダヤ系ロシア人で,のちに容共の疑いでジャーナリズムからは追放されている。
以下,メモ
p19 1945/12/10
農地改革法の準備 マッカーサー(本書ではマックアーサー)元帥は部下に指示を出して、部下はさらに煎じ詰めて新聞に載るようにしろと,自分の部下に指示を出した。「・・・書き上げたものは、マッカーサー元帥の他のあらゆる指令のご多分にもれず、この指令も人間の尊厳だとか、封建的発生の数世紀だとか、経済的束縛だとか、彼らの労働の果実だとか言ったお見事な決まり文句が随所に出てくる。しかし、これをを書き上げた将校たちは、これらの決まり文句が、日本人に爆発的な威力を持つことを、充分意識して書いたのである。」
p24 読売新聞の争議。新聞の民主化要求に、社主の正力松太郎は激怒し、先頭に立つ五人の幹部の首を切ったが、マッカーサーで命令が下り、戦犯として逮捕される。
p29 国家神道の廃止 天皇の神社への公式参拝は禁止されたが、「私的参拝」は禁止されない。公的か私的かは天皇自身の判断に任せられたので、つまり、見かけは今まで通り。
p30 12/16 近衛公爵の自害はこの日。ページを割いて詳しく経緯を記述している。周囲は公爵の自害を予想していたと感じた。
p66 酒田の警察署 署長に「追放された特高の連中はどうなったか」と聞いたら、米軍との連絡係をしているとの返事。
女子幼稚園に粘土製の手榴弾。文部省承認の張り紙。体操に使うと園長。
p88 1945年の大晦日から、信州・小諸周辺で「突然の捜索」旅行を計画したが、どこへ行っても事前に手を回されていて、接待の準備ができていた。
*日本には連絡網があり、占領軍のそれを上回っていた。日本人は一枚上手だった。
p105 農地改革について、小作人たちの意見を聞くために、信州・湯田中温泉の宿に泊まった。そこで戦中、社会主義者として投獄された経験者達と会食。席上、鷲見と言う男がI.W.W.の歌をうたうと言った。著者が聞き返すと、それは世界産業労働組合のことで、1905年に結成された米国の労働組合運動の象徴的な歌、The Preacher and the Slave.という歌だとわかった。著者にも聞き覚えのあるメロディなのだ。内親王が宿泊したこともあると言う宿で、著者は、まさかこのような歌を聴くとは思わなかったらしい。
p114 大阪の軍政部ロック少佐「財閥を解体したり、重い賠償を負わせたりすることは、かえって戦後の日本の統治をうまくいかないものにする。」と言った後、「まだ他にもある。自分自身をはぐらかすのはよそう。我々は強力な日本を必要とする。なぜなら我々は近い将来ロシアと愛大差なければならないし、同盟国を必要とするに至るだろう。日本がそれだ。」
p117 若松刑務所の視察。「刑務所内は甚だしい悪臭で、その烈しさは吐き気をもよおすほどだった。そこは17世紀の真っ只中にあった。」
p117 「日本は無方針に降伏したのではなかった。日本の支配者たちは降伏を決めるとすぐさま、その緻密かつ能率的な政府の全機構をあげて、まさに誓約せんとする勝利者への誓いをいかにごまかすかという仕事に没頭し始めた。彼らは降伏宣言と最初の米軍部隊到着との間の二週間の間隔を、甚だ巧みに利用した。証拠書類は焼却され、政府の資金は最も利用価値のある箇所にまき散らされ、高価な物資は隠匿された。また征服者の命令がどんなものであろうとも、政府機構はそこなわれないようにとの詳密なプランが立てられた。」
特高の関係者は追放の指令が出る前に全員辞職し、政府はすぐさま別の警察署長に任命した。
*著者は日本のどこに行っても、したたかな日本政府のやり方に遭遇し、バカにされたような気分を味わったことだろう。
p122 ホイットニー准将の「憲法制定会議」、・・「しかし新憲法は大体において、まさに廃棄されんとする明治憲法の型(パターン)を踏襲した。新憲法(草案)は2週間で作られた。」
ある日、ホイットニー准将、ケイディス大佐、フッセイ司令官は、松本烝治、吉田茂、通訳の白洲次郎に憲法草案を突きつけた。松本案はGHQに一蹴され、GHQ案を討議する前にこれを読むために15分間の時間を与えた。15分後、「日本人たちは、雷にうたれたような顔つきをしていた。通訳の役をつとめた白洲は、実際に口をあけても何の音も出てこなかったことが何回もあった。」(フッセイの詳細な記録による。)
*占領軍側当事者の、生々しい描写に臨場感がある。
マッカーサー自身が書いたという軍備放棄に関する規定のあるこの憲法を、筆者は、占領終了後には日本は何らかの口実を付けて軍隊を再建するだろうから、この欺瞞に満ちた憲法は断じて永続しない、と述べている。
*確かに軍隊は事実上再建されたが、憲法は一度も改正されなかった。
p126 熱海で87歳になる尾崎行雄と会見した。日本の将来についてしつこく質問したが、尊敬する尾崎の頭の中は半世紀遅れていた。
p155〜 1946年4月
*戦後初の総選挙「前夜」の騒然とした状況描写は見事で引き込まれる。
旧首相官邸(フランク・ロイド・ライト設計)に、左翼代表が幣原首相に会見を迫って騒動となる。警官はデモ隊に圧倒され、殴られたりし、拳銃を20発も威嚇発砲する。結局デモ隊に官邸に押し入られ、その時、群衆を追い払ったMPに抗議した荒畑寒村はPMに地面に叩き伏せられるなどあったため、翌日の首相との会見をこの時の怪我のために欠席している。新宿ではビルの瓦礫の横で加藤勘十、シズエ夫妻らが演説。二人は著者の友人だそうだ。また、造船所での野坂参三の演説も傍聴している。当然、公職追放候補の鳩山一郎の演説も聴いている。
p166
総選挙当日、投票所を視察。整然と投票が行われていることに、初めて見る米国人記者は感慨深げだが、筆者は戦前にも何度か総選挙を見ているので驚くに値しないという。立会人は戦前から立会人をしており、インタビューすると、立会人の感想は、「違いといえば婦人が投票しているという点だけだ」という。
p178
筆者は病床の石原莞爾を見舞う。筆者は石原に非常に興味を持っていた。優秀な指導者で、いずれ政界に復帰すると確信していたようだが、歴史はそうならなかった。
東京裁判を傍聴。例の大川周明が東条の頭を紙筒で叩いた件を目撃している。大川に会って話しも聞いているが、大川の行動は果たして梅毒のためだったのか、芝居だったのか、結局は分からない。
p206 総選挙後の国会で、 山口シヅエにインタビューしている。野坂参三よりも多くの票を獲得した。週5日の婦人労働と幼児への牛乳配給のためにたたかう、と述べた。美人でキビキビしていると、著者の評。
国会で尾崎行雄が演説したが、金つんぼの尾崎は、延々と続く演説にしびれを切らせた議員のヤジはまったく聞こえなかったようだ。
p216 マッカーサーの鶴の一声で、デモは全て中止に。
6月 通訳の松方ハル(ライシャワー夫人)と軽井沢へ家具の買い出し。そこで来栖三郎と彼の二人の娘にも会っている。
p247 1946年7月19日 広島
役所や病院を取材し、医師から生々しい被曝者の様子を知ることとなる。
被曝当時妊娠していた女性に会う。母親は火傷の痕が酷かったが、子供は正常に見えた。市街にいて無事だった12歳の少年に「アメリカ人をどう思う?」と聞くと、「・・その男の子は友達を見廻し石ころの山を眺め、それからわたしたちをみた。十二のこどもとしては大いに考えたにちがいなかった。「アメリカ人はいい。とても親切だ。」」
p292 茨城県磯原村
4人の村の代表と農業改革について話し合った。4人は米国の農業の現状について次々と質問し、夜中の2時過ぎまで続いた。著者がその熱心さに心を打たれた様子は、日本の農民に対する愛情のようなものを感じる。
井上日召 橘孝三郎 大川周明 三代陰謀家と呼び、水戸に隠棲していた橘孝三郎に面会する。橘のところへ行く途中、パンクしたジープのためにポンプを貸してくれたのは、血盟団事件で団琢磨を射殺した菱沼五郎だった。
p300 「私は考えた。世界中のどこにいったい、一人の外国人がパンクしたタイヤをダイナマイト製造犯人になおしてもらい、殺人犯所有のポンプを借りて空気を入れ、それをさらに、もう一人の刺客に案内されて政治テロの巨頭との会見に赴くことができるような国があろうか。日本はまったく幻想的な国だ。」
p310 新聞各社と放送局のストライキは、GHQの命令で中止されてしまう。新聞特派員の著者は本国に送る記事の冒頭「国会が公然と民主主義のレッテルをはられた新憲法を通過せしめた二時間後、日本の警察は罷業中の放送局員のデモを無残にも蹴散らした・・」と書いた。その後のゼネストも中止されたのは,私(阿部)でも知っていた。
p334 マッカーサー元帥は天皇と三度会見した。最初の会見では、元帥は「厳然と形式的な態度に終始した。」(有名なあの写真からもよく分かる)
「次の会見の際、元帥は初めて陛下と呼びかけた。」
マッカーサーの心情の変化はどこにあったのか。
占領軍内部での改革派と軍備派の確執、政策の不統一があったことがよく分かる。
朝鮮戦争前の、米国の極東での政策は、結局失敗だったと著者は見ている。日記はここまで。
ニッポン日記
マーク・ゲイン著 筑摩叢書12 筑摩書房 1963年
1945年12月に厚木飛行場に降り立ち、その後一年余り日本に滞在した、主としてシカゴ・サン紙に記事を書き送った記者が、占領時日本の体験を日記としてまとめたもの。
講和条約発効前に翻訳出版された。この本によると,米国はこれほどあっさり日本が全面降伏するとは思っていなかったようで,占領政策も憲法も急ごしらえ。さらに日本の政府はしたたかで,占領軍が進駐してくる前に,様々な策略を講じて戦犯にされそうな人員を配置しなおし,財閥の財産は見事に分散させ,大量の軍の物資は隠匿した。日本はわずかの期間に準備を整えてから占領軍を迎えた。翻弄されたのはむしろ占領軍だった。占領軍内部での政策の不一致や内部対立があり,日本政府はGHQの命令にもサボタージュで応戦するしで,ほとほと手を焼いたようだ。占領軍よりも既存の日本政府の情報網・指令系統の方が完璧で,ことごとく裏を書かれたことが随所にみられる。この本が戦後ほとんど顧みられていないのは残念。
日本の戦後は,GHQによって解放された左翼活動家が,かえってGHQの思惑とは別な方向へ進んでいくのを,GHQ自身が戸惑いながら押さえつけていたことがよくわかる。
筆者はGHQのやり方には常に批判的で,当局からはかなり睨まれていたようだ。
筆者の本名はモウ・ギンズバーグといい,亡命ユダヤ系ロシア人で,のちに容共の疑いでジャーナリズムからは追放されている。
以下,メモ
p19 1945/12/10
農地改革法の準備 マッカーサー(本書ではマックアーサー)元帥は部下に指示を出して、部下はさらに煎じ詰めて新聞に載るようにしろと,自分の部下に指示を出した。「・・・書き上げたものは、マッカーサー元帥の他のあらゆる指令のご多分にもれず、この指令も人間の尊厳だとか、封建的発生の数世紀だとか、経済的束縛だとか、彼らの労働の果実だとか言ったお見事な決まり文句が随所に出てくる。しかし、これをを書き上げた将校たちは、これらの決まり文句が、日本人に爆発的な威力を持つことを、充分意識して書いたのである。」
p24 読売新聞の争議。新聞の民主化要求に、社主の正力松太郎は激怒し、先頭に立つ五人の幹部の首を切ったが、マッカーサーで命令が下り、戦犯として逮捕される。
p29 国家神道の廃止 天皇の神社への公式参拝は禁止されたが、「私的参拝」は禁止されない。公的か私的かは天皇自身の判断に任せられたので、つまり、見かけは今まで通り。
p30 12/16 近衛公爵の自害はこの日。ページを割いて詳しく経緯を記述している。周囲は公爵の自害を予想していたと感じた。
p66 酒田の警察署 署長に「追放された特高の連中はどうなったか」と聞いたら、米軍との連絡係をしているとの返事。
女子幼稚園に粘土製の手榴弾。文部省承認の張り紙。体操に使うと園長。
p88 1945年の大晦日から、信州・小諸周辺で「突然の捜索」旅行を計画したが、どこへ行っても事前に手を回されていて、接待の準備ができていた。
*日本には連絡網があり、占領軍のそれを上回っていた。日本人は一枚上手だった。
p105 農地改革について、小作人たちの意見を聞くために、信州・湯田中温泉の宿に泊まった。そこで戦中、社会主義者として投獄された経験者達と会食。席上、鷲見と言う男がI.W.W.の歌をうたうと言った。著者が聞き返すと、それは世界産業労働組合のことで、1905年に結成された米国の労働組合運動の象徴的な歌、The Preacher and the Slave.という歌だとわかった。著者にも聞き覚えのあるメロディなのだ。内親王が宿泊したこともあると言う宿で、著者は、まさかこのような歌を聴くとは思わなかったらしい。
p114 大阪の軍政部ロック少佐「財閥を解体したり、重い賠償を負わせたりすることは、かえって戦後の日本の統治をうまくいかないものにする。」と言った後、「まだ他にもある。自分自身をはぐらかすのはよそう。我々は強力な日本を必要とする。なぜなら我々は近い将来ロシアと愛大差なければならないし、同盟国を必要とするに至るだろう。日本がそれだ。」
p117 若松刑務所の視察。「刑務所内は甚だしい悪臭で、その烈しさは吐き気をもよおすほどだった。そこは17世紀の真っ只中にあった。」
p117 「日本は無方針に降伏したのではなかった。日本の支配者たちは降伏を決めるとすぐさま、その緻密かつ能率的な政府の全機構をあげて、まさに誓約せんとする勝利者への誓いをいかにごまかすかという仕事に没頭し始めた。彼らは降伏宣言と最初の米軍部隊到着との間の二週間の間隔を、甚だ巧みに利用した。証拠書類は焼却され、政府の資金は最も利用価値のある箇所にまき散らされ、高価な物資は隠匿された。また征服者の命令がどんなものであろうとも、政府機構はそこなわれないようにとの詳密なプランが立てられた。」
特高の関係者は追放の指令が出る前に全員辞職し、政府はすぐさま別の警察署長に任命した。
*著者は日本のどこに行っても、したたかな日本政府のやり方に遭遇し、バカにされたような気分を味わったことだろう。
p122 ホイットニー准将の「憲法制定会議」、・・「しかし新憲法は大体において、まさに廃棄されんとする明治憲法の型(パターン)を踏襲した。新憲法(草案)は2週間で作られた。」
ある日、ホイットニー准将、ケイディス大佐、フッセイ司令官は、松本烝治、吉田茂、通訳の白洲次郎に憲法草案を突きつけた。松本案はGHQに一蹴され、GHQ案を討議する前にこれを読むために15分間の時間を与えた。15分後、「日本人たちは、雷にうたれたような顔つきをしていた。通訳の役をつとめた白洲は、実際に口をあけても何の音も出てこなかったことが何回もあった。」(フッセイの詳細な記録による。)
*占領軍側当事者の、生々しい描写に臨場感がある。
マッカーサー自身が書いたという軍備放棄に関する規定のあるこの憲法を、筆者は、占領終了後には日本は何らかの口実を付けて軍隊を再建するだろうから、この欺瞞に満ちた憲法は断じて永続しない、と述べている。
*確かに軍隊は事実上再建されたが、憲法は一度も改正されなかった。
p126 熱海で87歳になる尾崎行雄と会見した。日本の将来についてしつこく質問したが、尊敬する尾崎の頭の中は半世紀遅れていた。
p155〜 1946年4月
*戦後初の総選挙「前夜」の騒然とした状況描写は見事で引き込まれる。
旧首相官邸(フランク・ロイド・ライト設計)に、左翼代表が幣原首相に会見を迫って騒動となる。警官はデモ隊に圧倒され、殴られたりし、拳銃を20発も威嚇発砲する。結局デモ隊に官邸に押し入られ、その時、群衆を追い払ったMPに抗議した荒畑寒村はPMに地面に叩き伏せられるなどあったため、翌日の首相との会見をこの時の怪我のために欠席している。新宿ではビルの瓦礫の横で加藤勘十、シズエ夫妻らが演説。二人は著者の友人だそうだ。また、造船所での野坂参三の演説も傍聴している。当然、公職追放候補の鳩山一郎の演説も聴いている。
p166
総選挙当日、投票所を視察。整然と投票が行われていることに、初めて見る米国人記者は感慨深げだが、筆者は戦前にも何度か総選挙を見ているので驚くに値しないという。立会人は戦前から立会人をしており、インタビューすると、立会人の感想は、「違いといえば婦人が投票しているという点だけだ」という。
p178
筆者は病床の石原莞爾を見舞う。筆者は石原に非常に興味を持っていた。優秀な指導者で、いずれ政界に復帰すると確信していたようだが、歴史はそうならなかった。
東京裁判を傍聴。例の大川周明が東条の頭を紙筒で叩いた件を目撃している。大川に会って話しも聞いているが、大川の行動は果たして梅毒のためだったのか、芝居だったのか、結局は分からない。
p206 総選挙後の国会で、 山口シヅエにインタビューしている。野坂参三よりも多くの票を獲得した。週5日の婦人労働と幼児への牛乳配給のためにたたかう、と述べた。美人でキビキビしていると、著者の評。
国会で尾崎行雄が演説したが、金つんぼの尾崎は、延々と続く演説にしびれを切らせた議員のヤジはまったく聞こえなかったようだ。
p216 マッカーサーの鶴の一声で、デモは全て中止に。
6月 通訳の松方ハル(ライシャワー夫人)と軽井沢へ家具の買い出し。そこで来栖三郎と彼の二人の娘にも会っている。
p247 1946年7月19日 広島
役所や病院を取材し、医師から生々しい被曝者の様子を知ることとなる。
被曝当時妊娠していた女性に会う。母親は火傷の痕が酷かったが、子供は正常に見えた。市街にいて無事だった12歳の少年に「アメリカ人をどう思う?」と聞くと、「・・その男の子は友達を見廻し石ころの山を眺め、それからわたしたちをみた。十二のこどもとしては大いに考えたにちがいなかった。「アメリカ人はいい。とても親切だ。」」
p292 茨城県磯原村
4人の村の代表と農業改革について話し合った。4人は米国の農業の現状について次々と質問し、夜中の2時過ぎまで続いた。著者がその熱心さに心を打たれた様子は、日本の農民に対する愛情のようなものを感じる。
井上日召 橘孝三郎 大川周明 三代陰謀家と呼び、水戸に隠棲していた橘孝三郎に面会する。橘のところへ行く途中、パンクしたジープのためにポンプを貸してくれたのは、血盟団事件で団琢磨を射殺した菱沼五郎だった。
p300 「私は考えた。世界中のどこにいったい、一人の外国人がパンクしたタイヤをダイナマイト製造犯人になおしてもらい、殺人犯所有のポンプを借りて空気を入れ、それをさらに、もう一人の刺客に案内されて政治テロの巨頭との会見に赴くことができるような国があろうか。日本はまったく幻想的な国だ。」
p310 新聞各社と放送局のストライキは、GHQの命令で中止されてしまう。新聞特派員の著者は本国に送る記事の冒頭「国会が公然と民主主義のレッテルをはられた新憲法を通過せしめた二時間後、日本の警察は罷業中の放送局員のデモを無残にも蹴散らした・・」と書いた。その後のゼネストも中止されたのは,私(阿部)でも知っていた。
p334 マッカーサー元帥は天皇と三度会見した。最初の会見では、元帥は「厳然と形式的な態度に終始した。」(有名なあの写真からもよく分かる)
「次の会見の際、元帥は初めて陛下と呼びかけた。」
マッカーサーの心情の変化はどこにあったのか。
占領軍内部での改革派と軍備派の確執、政策の不統一があったことがよく分かる。
朝鮮戦争前の、米国の極東での政策は、結局失敗だったと著者は見ている。日記はここまで。
【今日の言葉】 ― 2015年11月25日
【今日の言葉】NHK 100分で名著から
人間の運命は、 人間の手中にある。
生きていく以上は、希望を作り出さなければならない。
J.P.サルトル
*サルトルの葬儀の写真。五万人もの市民が参列した。葬儀委員が「家族の方,棺の前へ」と促すと,「私たちは皆家族です!」と参列者から声がしたという。これほど惜しまれ,親しまれる知識人が,今の日本から出るのだろうか。
人間の運命は、 人間の手中にある。
生きていく以上は、希望を作り出さなければならない。
J.P.サルトル
*サルトルの葬儀の写真。五万人もの市民が参列した。葬儀委員が「家族の方,棺の前へ」と促すと,「私たちは皆家族です!」と参列者から声がしたという。これほど惜しまれ,親しまれる知識人が,今の日本から出るのだろうか。
読み終えた本「もういちど読む 山川 日本近代史」 ― 2015年11月10日

読み終えた本
もういちど読む 山川 日本近代史 鳥海 靖著 山川出版社(2013年)
中立的な立場から近代日本の歴史を冷静に述べているように思います。それは,「はじめに」によく示されています。
近代史をきちんと順序立てて読んだことがないので勉強になりました。また,歴史教科書では触れていない部分も多く書かれています。
---------
はじめに
本書は、幕末の黒船来航前後から第二次世界大戦の敗北に至る100年近くの日本の歩みについて、できるだけ国際社会のなかの日本と言う視野に立ちつつ概観し、近代日本の歴史的特色と問題点を探ろうとしたものである。
歴史の研究や叙述のうえで重要な事は、歴史の内在的理解であろう。歴史学は多くの場合、結末がわかっている事象を事後的に取り上げて、その原因を過去にさかのぼって究明し、その意味を解釈・論評する学問である。それは往々にして結果からの演繹的説明に陥りやすく,時代状況を無視して、今日的価値観により歴史を裁断する傾向を免れない。
しかし、歴史を内在的にとらえるためには、まず何よりも、その時代に生きた生身の人間たちがどのような価値基準に基づいて、何を考え、何を目標に行動したかを、歴史状況に即して理解することが必要不可欠といえよう。
このように考えれば、超歴史的な一元的価値基準に基づく、いわゆる「イデオロギー史観」 (例えば戦前の「皇国史観」,戦後の「人民史観」「階級闘争史観」など)は、ともすれば、事実を事実として多角的に歴史を直視する柔軟で広い視野を失わせ、単純な「善玉・悪玉的」歴史理解の弊に陥りかねない。それは、人間の英知の集積としての複雑で魅力に富んだ歴史諸相の様々な理解の可能性を、一つの正しい歴史認識の中に閉じ込めてしまうことになるのである。「歴史には神も悪魔も登場しない」という含蓄深いことわざの意味を、じっくりかみしめる必要があるように思われる。
著者
メモ
p95
帝国議会開設以来10年ほどで立憲政治は定着し、自由民権運動の流れをくむ正統派、明治憲法体制下に大きな地位を占め、日本における政党政治発展の基礎が築かれることになった。
日本の場合は、比較的短期間にそれほど大きな混乱もなく、藩閥勢力と政党勢力(自由民権派)の協力・妥協により、立憲政治が定着した。
p121
(明治期の)高度成長の秘密をどこに求めるかについて、様々な考え方があるが、寺子屋教育の伝統を引き継いだ学校教育の普及、とりわけ国民の読み書き能力の高さ、出身身分の階層に関係なく教育制度を通じて中下層の庶民が国家の指導階層まで上昇し得るようなタテの社会的流動性の高さ、「日本人の勤勉性」、宗教的束縛の欠如、そして、国民の大部分が同一民族からなり、同一言語を持ち、宗教的対立や民族紛争による流血もあまりないと言う状況のもとでの日本社会の同質性の高さなど、江戸時代以来の日本の様々な歴史的前提条件の重要性を考慮することが必要であろう。
p130
明治時代初期には、積極的な西洋文化の摂取や近代的変革の進行に伴って、日本の知識人の間に、日本の歴史や伝統的な文化を軽視する傾向が広まった。それはちょうど第二次世界大戦期の日本で、一時、知識人の間に戦前の日本に対する全面的な否定的評価が流行したのと、よく似た現象であった。
ベルツは、そうした現象を(次のように)観察し、自国の固有の歴史や文化を軽視する様な事では、かえって外国人たちの信頼を得られないだろうと批判している。(「ベルツ日記」 1876年10月25日)
p149
明治12年と明治19年のコレラの大流行では、それぞれ10万人以上の死者を出した。明治後期には港での検疫の強化、医療・衛生設備の改善、衛生思想の普及などによりコレラの死者は激減した。
その反面産業化の進行とともに肺結核による死者はかえって増加した。明治33年には年間7万2千人弱だった肺結核及び結核性疾患による死者は大正元年には11万4千人余りと1.6倍に増えた。若者の死亡原因で最も高い比率を占めるに至った。
p169
大正8年のパリ平和会議で、日本は5大国の一つとして、国際連盟加盟国は、人種差別を撤廃せよとの条項を盛り込もうとしたが、アメリカは人種差別問題は自国内の問題であり内政干渉にあたるとし、イギリスも白豪主義のオーストラリアの強い反対にあって、両国とも日本案には賛成しなかった。
p174
大正11年のワシントン海軍軍縮条約以降、陸軍も4個師団を廃止。それ以降、職業軍人に対する世間の目が厳しくなった。これがやがて不満を詰まらせ急進派軍人たちのテロやクーデターと言う直接行動を生み出す背景となった。
p183
国政選挙で女性参政権が認められたのは1893年のニュージーランドが最初。ドイツでは第一次大戦後,ヴァイマール憲法での1919年,アメリカでは翌年1920年,イギリスでも1928年。フランス・スイスでは,第二次大戦後の1945年・1971年だった。日本では1945年。
p223 「日本ファシズム」論をめぐって
このコラムでは「・・・確かに日本では,ファシズムの最大の特質と考えられるナチス流の強力な一党独裁体制を欠き,ヒトラーのような独裁者も出現せず,政治的反対派に対する徹底した大量粛清もなかった。天皇機関説の否認,国家総動員法の制定,大政翼賛会・翼賛政治会の成立(複数政党制の解消)などにより,明治憲法の立憲主義的側面は制定者の意に反して大幅に後退し,議会の権限は弱体化したが,憲法自体は改廃されなかったから,ドイツのナチス独裁やソ連の共産党独裁のような強力な独裁体制を作り上げることは困難だった。・・」
*日本の戦前の政治体制がよくわかる。確かに日本は軍国主義の国として進んでいってしまったが,ファシズムの国ではなかった。
もういちど読む 山川 日本近代史 鳥海 靖著 山川出版社(2013年)
中立的な立場から近代日本の歴史を冷静に述べているように思います。それは,「はじめに」によく示されています。
近代史をきちんと順序立てて読んだことがないので勉強になりました。また,歴史教科書では触れていない部分も多く書かれています。
---------
はじめに
本書は、幕末の黒船来航前後から第二次世界大戦の敗北に至る100年近くの日本の歩みについて、できるだけ国際社会のなかの日本と言う視野に立ちつつ概観し、近代日本の歴史的特色と問題点を探ろうとしたものである。
歴史の研究や叙述のうえで重要な事は、歴史の内在的理解であろう。歴史学は多くの場合、結末がわかっている事象を事後的に取り上げて、その原因を過去にさかのぼって究明し、その意味を解釈・論評する学問である。それは往々にして結果からの演繹的説明に陥りやすく,時代状況を無視して、今日的価値観により歴史を裁断する傾向を免れない。
しかし、歴史を内在的にとらえるためには、まず何よりも、その時代に生きた生身の人間たちがどのような価値基準に基づいて、何を考え、何を目標に行動したかを、歴史状況に即して理解することが必要不可欠といえよう。
このように考えれば、超歴史的な一元的価値基準に基づく、いわゆる「イデオロギー史観」 (例えば戦前の「皇国史観」,戦後の「人民史観」「階級闘争史観」など)は、ともすれば、事実を事実として多角的に歴史を直視する柔軟で広い視野を失わせ、単純な「善玉・悪玉的」歴史理解の弊に陥りかねない。それは、人間の英知の集積としての複雑で魅力に富んだ歴史諸相の様々な理解の可能性を、一つの正しい歴史認識の中に閉じ込めてしまうことになるのである。「歴史には神も悪魔も登場しない」という含蓄深いことわざの意味を、じっくりかみしめる必要があるように思われる。
著者
メモ
p95
帝国議会開設以来10年ほどで立憲政治は定着し、自由民権運動の流れをくむ正統派、明治憲法体制下に大きな地位を占め、日本における政党政治発展の基礎が築かれることになった。
日本の場合は、比較的短期間にそれほど大きな混乱もなく、藩閥勢力と政党勢力(自由民権派)の協力・妥協により、立憲政治が定着した。
p121
(明治期の)高度成長の秘密をどこに求めるかについて、様々な考え方があるが、寺子屋教育の伝統を引き継いだ学校教育の普及、とりわけ国民の読み書き能力の高さ、出身身分の階層に関係なく教育制度を通じて中下層の庶民が国家の指導階層まで上昇し得るようなタテの社会的流動性の高さ、「日本人の勤勉性」、宗教的束縛の欠如、そして、国民の大部分が同一民族からなり、同一言語を持ち、宗教的対立や民族紛争による流血もあまりないと言う状況のもとでの日本社会の同質性の高さなど、江戸時代以来の日本の様々な歴史的前提条件の重要性を考慮することが必要であろう。
p130
明治時代初期には、積極的な西洋文化の摂取や近代的変革の進行に伴って、日本の知識人の間に、日本の歴史や伝統的な文化を軽視する傾向が広まった。それはちょうど第二次世界大戦期の日本で、一時、知識人の間に戦前の日本に対する全面的な否定的評価が流行したのと、よく似た現象であった。
ベルツは、そうした現象を(次のように)観察し、自国の固有の歴史や文化を軽視する様な事では、かえって外国人たちの信頼を得られないだろうと批判している。(「ベルツ日記」 1876年10月25日)
p149
明治12年と明治19年のコレラの大流行では、それぞれ10万人以上の死者を出した。明治後期には港での検疫の強化、医療・衛生設備の改善、衛生思想の普及などによりコレラの死者は激減した。
その反面産業化の進行とともに肺結核による死者はかえって増加した。明治33年には年間7万2千人弱だった肺結核及び結核性疾患による死者は大正元年には11万4千人余りと1.6倍に増えた。若者の死亡原因で最も高い比率を占めるに至った。
p169
大正8年のパリ平和会議で、日本は5大国の一つとして、国際連盟加盟国は、人種差別を撤廃せよとの条項を盛り込もうとしたが、アメリカは人種差別問題は自国内の問題であり内政干渉にあたるとし、イギリスも白豪主義のオーストラリアの強い反対にあって、両国とも日本案には賛成しなかった。
p174
大正11年のワシントン海軍軍縮条約以降、陸軍も4個師団を廃止。それ以降、職業軍人に対する世間の目が厳しくなった。これがやがて不満を詰まらせ急進派軍人たちのテロやクーデターと言う直接行動を生み出す背景となった。
p183
国政選挙で女性参政権が認められたのは1893年のニュージーランドが最初。ドイツでは第一次大戦後,ヴァイマール憲法での1919年,アメリカでは翌年1920年,イギリスでも1928年。フランス・スイスでは,第二次大戦後の1945年・1971年だった。日本では1945年。
p223 「日本ファシズム」論をめぐって
このコラムでは「・・・確かに日本では,ファシズムの最大の特質と考えられるナチス流の強力な一党独裁体制を欠き,ヒトラーのような独裁者も出現せず,政治的反対派に対する徹底した大量粛清もなかった。天皇機関説の否認,国家総動員法の制定,大政翼賛会・翼賛政治会の成立(複数政党制の解消)などにより,明治憲法の立憲主義的側面は制定者の意に反して大幅に後退し,議会の権限は弱体化したが,憲法自体は改廃されなかったから,ドイツのナチス独裁やソ連の共産党独裁のような強力な独裁体制を作り上げることは困難だった。・・」
*日本の戦前の政治体制がよくわかる。確かに日本は軍国主義の国として進んでいってしまったが,ファシズムの国ではなかった。
読み終えた本 「ヒトはこうして増えてきた 20万年の人口変遷史」 ― 2015年10月28日

読み終えた本
「ヒトはこうして増えてきた 20万年の人口変遷史」
大塚柳太郎 新潮社 2015年
人類の人口の変遷については,
「銃・病原菌・鉄」上・下巻 ジャレド・ダイアモンド(草思社 2000年)
が非常に詳しく各時代の人口の増減の原因を検証している。
本書では,各時代の人口をいかに推定するかの手法についても述べられている。
期待したような「面白さ」はないものの,先進諸国での人口減少,途上国での人口急増が今後様々な国際紛争を生むかもしれず,考えさせられる。
内容(「BOOK」データベースより)
20万年前、アフリカで誕生したわれわれは穏やかに増えていくが、つい最近、突然の増加をみた。農耕が始まった約1万年前のわずか500万人が、文明が成立し始めた5500年前には1000万、265年前の産業革命で7億2000万となり、2015年には72億人。そしてこの先どう推移するのか?人口という切り口で人類史を眺めた新しいグローバル・ヒストリー。
メモ
p23 ホミニゼーションとサピエンテーション
第1ステージは中新世(2500万から500万年前)
第2ステージは500万年前からヒト属が出出現するまで
第3ステージは、初期のヒト属の時代から20万年前のホモサピエンスが誕生するまで
p36 血縁で結ばれた50人規模の狩猟採集集団をバンドという。この規模はチンパンジーの群れと同じである。
栄養状態が良くなったことで、ヒトは「自己家畜化」した。チンパンジーの授乳期間は4 年だが、ヒトは2年。
p139 成人の死亡年齢(骨から推定)
一万年前の旧石器時代 ♂33歳 ♀29歳
五千年前 ♂34歳 ♀30歳 遊牧から農耕へ 事故・外傷の減少
紀元2世紀のローマ~紀元1400年-1750年 ♂38-40歳 ♀31-37歳
p147
紀元元年ごろまでに特に人口が多かったのは、100万都市となったローマとアレクサンドリア、50万都市となったカルタゴと長安。
p160
今から1,800年前、コア・ユーラシアで人口の減少が起きた。この原因は、巨大帝国滅亡後の社会の混乱、農作物の不作や病気の罹患による死亡率の上昇が起きたため。一方、アフリカやアジアでは、人口増加が起きている。
p164
紀元500年頃から、中世の温暖化が始まり、世界的に人口が増加している。
p172
中世の人口増加の原因は、農業の道具や技術が広く普及したことによる。また11世紀から12世紀にかけて、冬ムギ(コムギとライムギ)の畑、夏ムギ(オオムギとオートムギ)の畑、休耕地に3分する、三圃式農法が開発されて普及した。小麦の収穫率は9世紀に3倍未満だったが、15世紀には5倍に達した。東南ユーラシアでのイネの生産性が向上し、中国南部に、ベトナム原産の占城稲と言われる、生産性の高いわせ品種が導入され、イネの二期作、イネとムギの二毛作が可能になった。日本では8~9世紀に7倍程度だった収穫率が、15世紀には20倍以上になったと推定されている。
p174
モンゴル帝国の侵略により中国・ユーラシア、中東の人口が減少した。ヨーロッパの人口減少はペストの流行による。14世紀には3回の流行があり、ヨーロッパ人口の3分の1が死亡した。それに飢饉が追い打ちをかけた。
ペスト菌は2600年前の中国南部が起源で、シルクロード経由で1000年かけて中東・ヨーロッパにもたらされた。
p215
日本の人口、13,000年前でほぼ2万人、6000年ほど前に26万人。
その後、次第に減少し4,000年前の縄文時代後期には10万を切った。
弥生時代は、60万人弱。奈良時代、725年に451万人。平安時代の800年に551万人。900年には644万人。
8世紀から10世紀における奈良、平安時代の律令制の下の水田と畑の開墾と整備が進んだことにより13世紀には人口密度が中国を超えた。
「ヒトはこうして増えてきた 20万年の人口変遷史」
大塚柳太郎 新潮社 2015年
人類の人口の変遷については,
「銃・病原菌・鉄」上・下巻 ジャレド・ダイアモンド(草思社 2000年)
が非常に詳しく各時代の人口の増減の原因を検証している。
本書では,各時代の人口をいかに推定するかの手法についても述べられている。
期待したような「面白さ」はないものの,先進諸国での人口減少,途上国での人口急増が今後様々な国際紛争を生むかもしれず,考えさせられる。
内容(「BOOK」データベースより)
20万年前、アフリカで誕生したわれわれは穏やかに増えていくが、つい最近、突然の増加をみた。農耕が始まった約1万年前のわずか500万人が、文明が成立し始めた5500年前には1000万、265年前の産業革命で7億2000万となり、2015年には72億人。そしてこの先どう推移するのか?人口という切り口で人類史を眺めた新しいグローバル・ヒストリー。
メモ
p23 ホミニゼーションとサピエンテーション
第1ステージは中新世(2500万から500万年前)
第2ステージは500万年前からヒト属が出出現するまで
第3ステージは、初期のヒト属の時代から20万年前のホモサピエンスが誕生するまで
p36 血縁で結ばれた50人規模の狩猟採集集団をバンドという。この規模はチンパンジーの群れと同じである。
栄養状態が良くなったことで、ヒトは「自己家畜化」した。チンパンジーの授乳期間は4 年だが、ヒトは2年。
p139 成人の死亡年齢(骨から推定)
一万年前の旧石器時代 ♂33歳 ♀29歳
五千年前 ♂34歳 ♀30歳 遊牧から農耕へ 事故・外傷の減少
紀元2世紀のローマ~紀元1400年-1750年 ♂38-40歳 ♀31-37歳
p147
紀元元年ごろまでに特に人口が多かったのは、100万都市となったローマとアレクサンドリア、50万都市となったカルタゴと長安。
p160
今から1,800年前、コア・ユーラシアで人口の減少が起きた。この原因は、巨大帝国滅亡後の社会の混乱、農作物の不作や病気の罹患による死亡率の上昇が起きたため。一方、アフリカやアジアでは、人口増加が起きている。
p164
紀元500年頃から、中世の温暖化が始まり、世界的に人口が増加している。
p172
中世の人口増加の原因は、農業の道具や技術が広く普及したことによる。また11世紀から12世紀にかけて、冬ムギ(コムギとライムギ)の畑、夏ムギ(オオムギとオートムギ)の畑、休耕地に3分する、三圃式農法が開発されて普及した。小麦の収穫率は9世紀に3倍未満だったが、15世紀には5倍に達した。東南ユーラシアでのイネの生産性が向上し、中国南部に、ベトナム原産の占城稲と言われる、生産性の高いわせ品種が導入され、イネの二期作、イネとムギの二毛作が可能になった。日本では8~9世紀に7倍程度だった収穫率が、15世紀には20倍以上になったと推定されている。
p174
モンゴル帝国の侵略により中国・ユーラシア、中東の人口が減少した。ヨーロッパの人口減少はペストの流行による。14世紀には3回の流行があり、ヨーロッパ人口の3分の1が死亡した。それに飢饉が追い打ちをかけた。
ペスト菌は2600年前の中国南部が起源で、シルクロード経由で1000年かけて中東・ヨーロッパにもたらされた。
p215
日本の人口、13,000年前でほぼ2万人、6000年ほど前に26万人。
その後、次第に減少し4,000年前の縄文時代後期には10万を切った。
弥生時代は、60万人弱。奈良時代、725年に451万人。平安時代の800年に551万人。900年には644万人。
8世紀から10世紀における奈良、平安時代の律令制の下の水田と畑の開墾と整備が進んだことにより13世紀には人口密度が中国を超えた。
読み終えた本「利己的な遺伝子」リチャード・ドーキンス ― 2015年10月02日
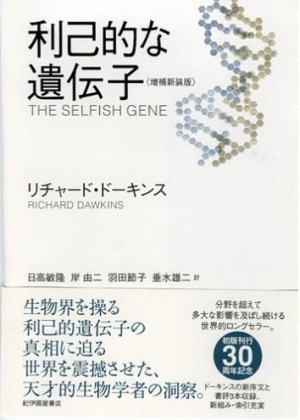
利己的な遺伝子
リチャード・ドーキンス
紀伊國屋書店; 増補新装版 2006年
1976年に初版が出ているので,30年経ってやっと読んだ。そういえば,昔,小檜山さんが自著で「ドーキンス的には云々・」ということを書かれていたけれど,読んだことがなかったので,どういうことなのか,当時はわからなかった。
「遺伝子は利己的である。生物が利他的行動をとったとしても,それは結局は遺伝子を都合よく残すための利己的行動である」というようなことを読むにつけ,元になったこの本を読まなければなぁと思っていた。
遺伝学の話でも,分子生物学の話でもなく,ドーキンスの哲学的思索の書,という感じがする。「利己的遺伝子」という考えはドーキンスのオリジナルではないが,本書によって広く知られるようになった。
メモ
「生物体は、利己的な遺伝子たちによって盲目的にプログラムされた機械である。」とか,
生物は遺伝子を次の世代に運ぶための乗り物にすぎない,というのはいかにも刺激的である。
また,遺伝子に対して,社会・文化(例えば習慣,技能,物語など)を受け継いで複製していくものを「ミーム:meme」と呼んだ。
p407 人間やワラジムシのような進んだ動物の複雑な器官は祖先たちの単純な器官から徐々に段階的に進化してきた。しかし、祖先の器官は、刀を打って鍬の刃にするように、文字通りの意味で子孫の器官に変化していったのでは無い。
の「刀を打って鍬の刃にするように・・」は,「かれらはその劍をうちかへて鍬となし、その槍をうちかへて鎌となし、國は國にむかひて劍をあげず、戦闘(たたかひ)のことを再びまなばざるべし」イザヤ書第二章四節からの引用だろう。
キリスト教圏の人間は,時にさりげなく聖書から引用するが,たまたまこの語句は知っていたからわかったのだけど,ほとんどはスルーしてしまっているのだろう。『神は妄想である――宗教との決別』を書いた人でも,このようなことをするのだ。
p416 宇宙のどんな場所であれ、生命が生じるために存在しなければならなかった唯一の実態は、不滅の自己複製子である。
*例え,生命の基本構成原子が炭素から硅素に変わったとしても,同じように「利己的な自己複製子」を運ぶ乗り物であることは変わりがないのかもしれない。
自分の生命観というものが,多少変わったように思う。
リチャード・ドーキンス
紀伊國屋書店; 増補新装版 2006年
1976年に初版が出ているので,30年経ってやっと読んだ。そういえば,昔,小檜山さんが自著で「ドーキンス的には云々・」ということを書かれていたけれど,読んだことがなかったので,どういうことなのか,当時はわからなかった。
「遺伝子は利己的である。生物が利他的行動をとったとしても,それは結局は遺伝子を都合よく残すための利己的行動である」というようなことを読むにつけ,元になったこの本を読まなければなぁと思っていた。
遺伝学の話でも,分子生物学の話でもなく,ドーキンスの哲学的思索の書,という感じがする。「利己的遺伝子」という考えはドーキンスのオリジナルではないが,本書によって広く知られるようになった。
メモ
「生物体は、利己的な遺伝子たちによって盲目的にプログラムされた機械である。」とか,
生物は遺伝子を次の世代に運ぶための乗り物にすぎない,というのはいかにも刺激的である。
また,遺伝子に対して,社会・文化(例えば習慣,技能,物語など)を受け継いで複製していくものを「ミーム:meme」と呼んだ。
p407 人間やワラジムシのような進んだ動物の複雑な器官は祖先たちの単純な器官から徐々に段階的に進化してきた。しかし、祖先の器官は、刀を打って鍬の刃にするように、文字通りの意味で子孫の器官に変化していったのでは無い。
の「刀を打って鍬の刃にするように・・」は,「かれらはその劍をうちかへて鍬となし、その槍をうちかへて鎌となし、國は國にむかひて劍をあげず、戦闘(たたかひ)のことを再びまなばざるべし」イザヤ書第二章四節からの引用だろう。
キリスト教圏の人間は,時にさりげなく聖書から引用するが,たまたまこの語句は知っていたからわかったのだけど,ほとんどはスルーしてしまっているのだろう。『神は妄想である――宗教との決別』を書いた人でも,このようなことをするのだ。
p416 宇宙のどんな場所であれ、生命が生じるために存在しなければならなかった唯一の実態は、不滅の自己複製子である。
*例え,生命の基本構成原子が炭素から硅素に変わったとしても,同じように「利己的な自己複製子」を運ぶ乗り物であることは変わりがないのかもしれない。
自分の生命観というものが,多少変わったように思う。

最近のコメント