読み終えた本 遠い崖 第4巻 慶喜登場 ― 2018年05月30日
読み終えた本
遠い崖 第4巻 慶喜登場
ーアーネスト・サトウ日記抄ー 萩原延壽(1999年)
パークスは日本の内政には不干渉(英仏蘭米ともに)の立場を取ったが、第二次長州戦争では2隻あったフランスの軍艦は、本国へ引き上げてしまったので、フランスは事実上幕府を支援できなかった。
横浜の大火では、サトウ等の住まいが焼け、特にサトウは多くの蔵書や原稿を失った。本国への報告にある損害リストには拳銃(コルト)が入っている。
1866年、サトウは長崎で、シーボルト(父)が所有していた山荘を訪れている。その後、通訳官シーボルトの姉に会っている。姉はすなわち、父シーボルトと楠本滝との間に生まれた「伊禰」である。父シーボルトはこの2ヶ月前に亡くなっている。
慶喜が新将軍となるに当たり、パークス等外国公使と四人の外国奉行が協議したが、この時、将軍の資格と地位がはっきりとし、それまでの将軍をMajesty と呼ぶ事は相応しくないとし、天皇にのみ相応しいと考えるようになった。将軍に対してはHighnessが適当であるとした。実際には慶喜と四カ国公使が謁見した際、パークスはHighnessの呼称に固執したが、他の3カ国はMajestyと呼んだ。
p174
サトウの「一外交官の見た明治維新」は、昭和35年まで禁書扱いだった。孝明天皇毒殺説の為。
p210
将軍慶喜と各国大使との謁見に同行したサトウは、大阪の街を散策、三井呉服店(三越の前身)の前を通った時「店は数え切れないほどの行灯の光で照らし出され、実に美しい眺めであった。」と述べている。
p228
サトウと二等書記官ミットフォードは、小松帯刀らと会談した際、小松から英国の介入を望まれたが、政治的中立を保つという方針から、パークスははっきりとこれを拒絶している。
p277
大阪での徳川慶喜との会見を前に、パークスはロッシュが大阪と江戸の開市を、外国人が住むには危険が多いという理由で除外しようとしている点を問題にしている。パークスは外相への報告で「武器を携帯した始末におえない階級がいるところでは、常にある種の危険がつきまとうであろうが、この階級はたんに江戸と大阪にいるばかりでなく、日本の至る所にいるのである。」と述べている。だが、大阪は商人が多いので比較的安全と言っている。また、フランスは武士階級をかなり恐れていた事がうかがえる。
この当時、日本が「支那」のようには扱えない事が英国にはよく分かっていたのだろう。事実、そうならなかった。
サトウは、比較的暇な時期に、パークス等を引き連れて、船で熱海に行き温泉を堪能し、箱根の関所を見て、小田原を旅している。当時の旅籠の様子や、オールコックが残した石碑(得意の漢字で彫られている)の描写が興味深い。オールコックの愛犬が間欠泉の熱湯を浴びて死んでしまい、その死を悼んだ石碑は今でもあるという。
サトウは箱根旅行の後、泉岳寺近くの寺に住む事となる。公使館はこの寺の下にあった。この頃、日記に英国留学生の件で「安房」として登場するのが軍艦奉行、勝安房守だ。この頃から勝とは親密な関係となる。
サトウはワーグマンや従者とともに日本食を食べ、湊屋とい女郎屋に扮装して出かけている。サトウは人々が自分達のことを、若い頃にイギリスに行った事のある薩摩藩士で、日本人と区別が付かなくなったと噂していると書いている。ワーグマンも、サトウ同様、日本語が堪能だった事だろう。
p350〜
1867年4月末から5月にかけて、大阪城において将軍慶喜と外国公使謁見が行われた。この時、英国公使パークスは、フランス風の豪華な晩餐会が終わった後の別室で、壁に掛かった「三十六歌仙」の絵の説明を、サトウから受けた。サトウは詳しく説明し、それをみて感銘を受けた慶喜はそのなかの「伊勢」をパークスに贈った。パークスが揃いのものからなので辞退するが、慶喜は、空白ができたとしても、その一枚が今英国公使の手に渡っていることは私の喜びである、と述べて、パークスを感激させた。
このことは、新村出の養父、新村猛雄が当時、小姓頭取として慶喜に仕えていたためこの場に臨席していたので孫の出の知ることとなった。同席していた幕府側の人間も、絵を次々にパークスに説明したサトウに驚嘆したという。(横須賀製鉄所ドック起工(1871年竣工)はこの年の4月7日だった。)
*なかなか読み終えなかったが、特に最後のあたりは当時の手紙が多数引用されており、候文を読むのは大変で、ベッドで読んでいるとすぐ眠くなるために遅々として進まなかった。(^_^;)
遠い崖 第4巻 慶喜登場
ーアーネスト・サトウ日記抄ー 萩原延壽(1999年)
パークスは日本の内政には不干渉(英仏蘭米ともに)の立場を取ったが、第二次長州戦争では2隻あったフランスの軍艦は、本国へ引き上げてしまったので、フランスは事実上幕府を支援できなかった。
横浜の大火では、サトウ等の住まいが焼け、特にサトウは多くの蔵書や原稿を失った。本国への報告にある損害リストには拳銃(コルト)が入っている。
1866年、サトウは長崎で、シーボルト(父)が所有していた山荘を訪れている。その後、通訳官シーボルトの姉に会っている。姉はすなわち、父シーボルトと楠本滝との間に生まれた「伊禰」である。父シーボルトはこの2ヶ月前に亡くなっている。
慶喜が新将軍となるに当たり、パークス等外国公使と四人の外国奉行が協議したが、この時、将軍の資格と地位がはっきりとし、それまでの将軍をMajesty と呼ぶ事は相応しくないとし、天皇にのみ相応しいと考えるようになった。将軍に対してはHighnessが適当であるとした。実際には慶喜と四カ国公使が謁見した際、パークスはHighnessの呼称に固執したが、他の3カ国はMajestyと呼んだ。
p174
サトウの「一外交官の見た明治維新」は、昭和35年まで禁書扱いだった。孝明天皇毒殺説の為。
p210
将軍慶喜と各国大使との謁見に同行したサトウは、大阪の街を散策、三井呉服店(三越の前身)の前を通った時「店は数え切れないほどの行灯の光で照らし出され、実に美しい眺めであった。」と述べている。
p228
サトウと二等書記官ミットフォードは、小松帯刀らと会談した際、小松から英国の介入を望まれたが、政治的中立を保つという方針から、パークスははっきりとこれを拒絶している。
p277
大阪での徳川慶喜との会見を前に、パークスはロッシュが大阪と江戸の開市を、外国人が住むには危険が多いという理由で除外しようとしている点を問題にしている。パークスは外相への報告で「武器を携帯した始末におえない階級がいるところでは、常にある種の危険がつきまとうであろうが、この階級はたんに江戸と大阪にいるばかりでなく、日本の至る所にいるのである。」と述べている。だが、大阪は商人が多いので比較的安全と言っている。また、フランスは武士階級をかなり恐れていた事がうかがえる。
この当時、日本が「支那」のようには扱えない事が英国にはよく分かっていたのだろう。事実、そうならなかった。
サトウは、比較的暇な時期に、パークス等を引き連れて、船で熱海に行き温泉を堪能し、箱根の関所を見て、小田原を旅している。当時の旅籠の様子や、オールコックが残した石碑(得意の漢字で彫られている)の描写が興味深い。オールコックの愛犬が間欠泉の熱湯を浴びて死んでしまい、その死を悼んだ石碑は今でもあるという。
サトウは箱根旅行の後、泉岳寺近くの寺に住む事となる。公使館はこの寺の下にあった。この頃、日記に英国留学生の件で「安房」として登場するのが軍艦奉行、勝安房守だ。この頃から勝とは親密な関係となる。
サトウはワーグマンや従者とともに日本食を食べ、湊屋とい女郎屋に扮装して出かけている。サトウは人々が自分達のことを、若い頃にイギリスに行った事のある薩摩藩士で、日本人と区別が付かなくなったと噂していると書いている。ワーグマンも、サトウ同様、日本語が堪能だった事だろう。
p350〜
1867年4月末から5月にかけて、大阪城において将軍慶喜と外国公使謁見が行われた。この時、英国公使パークスは、フランス風の豪華な晩餐会が終わった後の別室で、壁に掛かった「三十六歌仙」の絵の説明を、サトウから受けた。サトウは詳しく説明し、それをみて感銘を受けた慶喜はそのなかの「伊勢」をパークスに贈った。パークスが揃いのものからなので辞退するが、慶喜は、空白ができたとしても、その一枚が今英国公使の手に渡っていることは私の喜びである、と述べて、パークスを感激させた。
このことは、新村出の養父、新村猛雄が当時、小姓頭取として慶喜に仕えていたためこの場に臨席していたので孫の出の知ることとなった。同席していた幕府側の人間も、絵を次々にパークスに説明したサトウに驚嘆したという。(横須賀製鉄所ドック起工(1871年竣工)はこの年の4月7日だった。)
*なかなか読み終えなかったが、特に最後のあたりは当時の手紙が多数引用されており、候文を読むのは大変で、ベッドで読んでいるとすぐ眠くなるために遅々として進まなかった。(^_^;)
読み終えた本 遠い崖 第3巻 英国策論 ― 2018年03月07日
読み終えた本
遠い崖 第3巻 英国策論
メモ
*オールコックの後を継いだパークスの銅像が、戦前の上海共同租界に建っていたが、中華人民共和国成立と同時に撤去されている。
*パークスがカントンの領事だった1856年、アロー号事件が勃発し、英仏連合軍が北京に侵攻したが、交渉が決裂して捕虜になってしまう。捕らえられた40名のうち、半数は虐殺されたが、パークスは無事帰還した。牢で鎖に繋がれて天井から吊るされたそうで、帰国してからは英雄扱い。Sir の称号も得ている。
*パークスは14歳の時から中国で暮らしており、初等教育しか正規の教育を受けていない。しかし、20年以上も極東外交に従事していた。日本に赴任する前は、日本人も中国人も同じアジア人と見ていた。
*サトウはパークスと函館へ行っている。そこでアイヌに会い、アイヌ語の単語を聞き出そうとしたが、その主人の漁夫に勘違いされて、邪魔をされてしまっている。
*函館ではブラキストンに会っている。(p48)彼を下等な人間と評しているのは何故だろうか。本書のこの項では、ブラキストン線で著名なブラキストンについては、何も触れていないのが奇妙。筆者が知らないずが無いと思うが、あえて歴史に関係ないとしてスルーしたのか。ブラキストンは他にシマフクロウの学名(Ketupa blakistoni)に名を留めている。
「それから製材所か何かをやっているブレキストン(Blakiston )。かつては陸軍砲兵大尉で、紳士だった男であるが、今は製材業者で、自分から進んで下等の人間に身を落としている。それが彼の性に合うためらしい。」
「そういえば、当地の外国人社会に触れた際、私にポニーを貸してくれたダン(Dun)のことを書くのを忘れていた。彼は善良な性質の男だが、残念ながら、他の外国人と同じように、下等な人間の部類に属する。(p49)
*このDunはEdwin Dunのことと思われ、(獣医師で明治期のお雇い外国人。開拓使に雇用され、北海道における畜産業の発展に大きく貢献した。後に駐日米国公使。Wikipedia)
ブラキストンはその後アメリカに移住し、ダンの娘と結婚している。ダンは北海道の畜産・酪農に多大な功績を残しており、日本人と結婚している。(1883年勲五等双光旭日章)これ程の人物を下等な人間とどうして評価したのか疑問が残る。
英国の外交手段を見ていると、彼らは「砲艦政策:Gunboat Policy 」で臨んでおり、幕府・雄藩も、砲艦の威圧に対して為すすべもなかった。西欧列強に対する当時の日本の立場は、先の大戦の敗戦を期に今も続いていると感じる。
昨今の中国の強気外交は、日本が感じている西欧に対する劣等意識の裏返しだと思うと納得できる。中国の感じているそれは、日本の比ではないだろう。だからといって、今の中国外交を支持するものでは断じて無いが。
薩摩から神戸に戻ってきた汽船胡蝶丸を訪ねたサトウに同行したシーボルト(アレキサンダー)は、島津久光と思われる人物を6フィートの巨漢だと述べているが、実はそれは西郷吉之助のことだった。この時、アオキと名乗る役人にも会っているが、その人物はどうも坂本龍馬だったらしい。
兵庫沖会談で幕府側で主導的役割を果たしたのは、小栗上野介だった。
(p187) この時点で、パークスは薩長とも通じていて、情勢を正しく理解していたのに比べ、ロシュは幕府への信頼が厚く、薩長側の真意を理解していなかった。
サトウは、ジャパン・タイムズへ、公使館の許可なく無署名で論説を投稿していた。(p222) これが、英国策論の原文となった記事だった。サトウは将軍の地位を以下のように考えていた。
「われわれは、次のことを心に銘記しておかなければならない。すなわち、将軍は、日本の政府を指導していると公言しているけれども、実際には、諸侯連合の首席に過ぎず我々との最初の条約が結ばれた時にも、そうであったに過ぎなかったと言うこと、そして、将軍が一国の支配者と言う肩書きを僭称するのは、この国の半分ほどしか、彼の管轄に属していないのだから、実に僭越至極な行為であったと言うことである。」
この時点で兵庫の開港は、条約により2年後に迫っていた。
Wikipedia によれば、
「英国策論(えいこく さくろん)とは、アーネスト・サトウが1866年に無題・無署名でジャパン・タイムスに寄稿した3つの記事を和訳したものである。「英国策論」と名付けられ、広く読まれた。イギリスの対日政策を示すものとみなされ、明治維新に大きな影響を与えた。
『英国策論』の骨子は以下の通り。
1. 将軍は主権者ではなく諸侯連合の首席にすぎず、現行の条約はその将軍とだけ結ばれたものである。したがって現行条約のほとんどの条項は主権者ではない将軍には実行できないものである。
2. 独立大名たちは外国との貿易に大きな関心をもっている。
3. 現行条約を廃し、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸侯連合に移すべきである。
*これは、パークスが「この条約は将軍とだけではなく、日本と結ばれているものである。」と言う考えとは違い、この条約の問題点を鋭く指摘したものであった。パークスは公使として、その様な立場を取らざるを得ない。
英国策論は、サトウの知らない間に多くの写本が出回り、多くの大名の家臣たちが持つこととなり、直ぐにに出版されている。
幕府は陸軍の訓練はフランスに任せたが、海軍はイギリスに要請した。パークスは間違っても海軍までフランスに訓練させないよう、ロッシュにも根回しし、しっかりと手を打った。
パークス一行の薩摩訪問。グラバー、通訳のシーボルトも同行している。市内を見物の後、島津久光にも会っている。藩主茂久は、薩英戦争の事は忘れて友好関係を築こう、と挨拶。宴席は盛大で、45品の精巧を極めた日本の珍味、日本酒、シャンパン、シェリー酒、ビールが用意された。ウィリスの評価は非常に低かった。海産物が嫌いなのだろう。
p319 パークスは旗艦で宇和島に訪れ、藩主の接待を藩主の家族ぐるみで受ける。藩主の主治医が、シーボルト(父)の娘である「いね」で、通訳としてシーボルト(長男のアレキサンダー)が居たため話題に上った。「いね」に会ったかどうかは資料からは不明。
*次は「慶喜登場」
遠い崖 第3巻 英国策論
メモ
*オールコックの後を継いだパークスの銅像が、戦前の上海共同租界に建っていたが、中華人民共和国成立と同時に撤去されている。
*パークスがカントンの領事だった1856年、アロー号事件が勃発し、英仏連合軍が北京に侵攻したが、交渉が決裂して捕虜になってしまう。捕らえられた40名のうち、半数は虐殺されたが、パークスは無事帰還した。牢で鎖に繋がれて天井から吊るされたそうで、帰国してからは英雄扱い。Sir の称号も得ている。
*パークスは14歳の時から中国で暮らしており、初等教育しか正規の教育を受けていない。しかし、20年以上も極東外交に従事していた。日本に赴任する前は、日本人も中国人も同じアジア人と見ていた。
*サトウはパークスと函館へ行っている。そこでアイヌに会い、アイヌ語の単語を聞き出そうとしたが、その主人の漁夫に勘違いされて、邪魔をされてしまっている。
*函館ではブラキストンに会っている。(p48)彼を下等な人間と評しているのは何故だろうか。本書のこの項では、ブラキストン線で著名なブラキストンについては、何も触れていないのが奇妙。筆者が知らないずが無いと思うが、あえて歴史に関係ないとしてスルーしたのか。ブラキストンは他にシマフクロウの学名(Ketupa blakistoni)に名を留めている。
「それから製材所か何かをやっているブレキストン(Blakiston )。かつては陸軍砲兵大尉で、紳士だった男であるが、今は製材業者で、自分から進んで下等の人間に身を落としている。それが彼の性に合うためらしい。」
「そういえば、当地の外国人社会に触れた際、私にポニーを貸してくれたダン(Dun)のことを書くのを忘れていた。彼は善良な性質の男だが、残念ながら、他の外国人と同じように、下等な人間の部類に属する。(p49)
*このDunはEdwin Dunのことと思われ、(獣医師で明治期のお雇い外国人。開拓使に雇用され、北海道における畜産業の発展に大きく貢献した。後に駐日米国公使。Wikipedia)
ブラキストンはその後アメリカに移住し、ダンの娘と結婚している。ダンは北海道の畜産・酪農に多大な功績を残しており、日本人と結婚している。(1883年勲五等双光旭日章)これ程の人物を下等な人間とどうして評価したのか疑問が残る。
英国の外交手段を見ていると、彼らは「砲艦政策:Gunboat Policy 」で臨んでおり、幕府・雄藩も、砲艦の威圧に対して為すすべもなかった。西欧列強に対する当時の日本の立場は、先の大戦の敗戦を期に今も続いていると感じる。
昨今の中国の強気外交は、日本が感じている西欧に対する劣等意識の裏返しだと思うと納得できる。中国の感じているそれは、日本の比ではないだろう。だからといって、今の中国外交を支持するものでは断じて無いが。
薩摩から神戸に戻ってきた汽船胡蝶丸を訪ねたサトウに同行したシーボルト(アレキサンダー)は、島津久光と思われる人物を6フィートの巨漢だと述べているが、実はそれは西郷吉之助のことだった。この時、アオキと名乗る役人にも会っているが、その人物はどうも坂本龍馬だったらしい。
兵庫沖会談で幕府側で主導的役割を果たしたのは、小栗上野介だった。
(p187) この時点で、パークスは薩長とも通じていて、情勢を正しく理解していたのに比べ、ロシュは幕府への信頼が厚く、薩長側の真意を理解していなかった。
サトウは、ジャパン・タイムズへ、公使館の許可なく無署名で論説を投稿していた。(p222) これが、英国策論の原文となった記事だった。サトウは将軍の地位を以下のように考えていた。
「われわれは、次のことを心に銘記しておかなければならない。すなわち、将軍は、日本の政府を指導していると公言しているけれども、実際には、諸侯連合の首席に過ぎず我々との最初の条約が結ばれた時にも、そうであったに過ぎなかったと言うこと、そして、将軍が一国の支配者と言う肩書きを僭称するのは、この国の半分ほどしか、彼の管轄に属していないのだから、実に僭越至極な行為であったと言うことである。」
この時点で兵庫の開港は、条約により2年後に迫っていた。
Wikipedia によれば、
「英国策論(えいこく さくろん)とは、アーネスト・サトウが1866年に無題・無署名でジャパン・タイムスに寄稿した3つの記事を和訳したものである。「英国策論」と名付けられ、広く読まれた。イギリスの対日政策を示すものとみなされ、明治維新に大きな影響を与えた。
『英国策論』の骨子は以下の通り。
1. 将軍は主権者ではなく諸侯連合の首席にすぎず、現行の条約はその将軍とだけ結ばれたものである。したがって現行条約のほとんどの条項は主権者ではない将軍には実行できないものである。
2. 独立大名たちは外国との貿易に大きな関心をもっている。
3. 現行条約を廃し、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸侯連合に移すべきである。
*これは、パークスが「この条約は将軍とだけではなく、日本と結ばれているものである。」と言う考えとは違い、この条約の問題点を鋭く指摘したものであった。パークスは公使として、その様な立場を取らざるを得ない。
英国策論は、サトウの知らない間に多くの写本が出回り、多くの大名の家臣たちが持つこととなり、直ぐにに出版されている。
幕府は陸軍の訓練はフランスに任せたが、海軍はイギリスに要請した。パークスは間違っても海軍までフランスに訓練させないよう、ロッシュにも根回しし、しっかりと手を打った。
パークス一行の薩摩訪問。グラバー、通訳のシーボルトも同行している。市内を見物の後、島津久光にも会っている。藩主茂久は、薩英戦争の事は忘れて友好関係を築こう、と挨拶。宴席は盛大で、45品の精巧を極めた日本の珍味、日本酒、シャンパン、シェリー酒、ビールが用意された。ウィリスの評価は非常に低かった。海産物が嫌いなのだろう。
p319 パークスは旗艦で宇和島に訪れ、藩主の接待を藩主の家族ぐるみで受ける。藩主の主治医が、シーボルト(父)の娘である「いね」で、通訳としてシーボルト(長男のアレキサンダー)が居たため話題に上った。「いね」に会ったかどうかは資料からは不明。
*次は「慶喜登場」
読み終えた本 遠い崖 第2巻 薩英戦争 ― 2018年02月04日

読み終えた本
遠い崖 第2巻 薩英戦争
ーアーネスト・サトウ日記抄ー 萩原延壽
生麦事件の賠償金は、紆余曲折の末、英国の要求通りの額が幕府負担分が支払われたが、薩摩藩は依然支払いを引き延ばしていた。交渉のため、7隻の英国艦隊は、横浜から5日掛かって鹿児島に着いた。石炭節約のため大部分を帆走したため。このとき、生麦事件の賠償金の一部は積まれたままだった。
艦隊の砲の総数は、90門だった。
幕府の役人らは艦隊への同乗を断り、幕府の船で英国艦隊の後を追ったのは、薩英の仲介役にでもなるつもりかと思いきや、到着は薩英戦争終了後。大幅に遅れたのは非力な60馬力のエンジンにあるのではなく、幕府内の開国派と攘夷派の板挟みによる折衷案の結果だったらしい。
薩摩は英国との貿易を望んでおり、この交渉をその為に利用する腹積もりがあったが、英国側の賠償要求書にあった事件の首謀者の首を差し出せ、という項目が、責任者(すなわち島津三郎こと久光)の首と幕府側が勝手に解釈した文書が存在した。
鹿児島湾に投錨した旗艦に、薩摩の役人達は小船で何度も来艦し、上陸要請や物資の補給を申し入れたが、英国側に拒絶された。うち、40名程の、回答書を持参した藩の高官と称する一行も乗艦したが、実は生麦事件の当事者2名も加わっており、居合わせた英国公使と艦隊司令官を斬り殺す手筈だった。陸上からの決行の合図を待っていたが、急遽、引き返す事になり、公使らは命拾いしたという。この計画には久光も賛同していた。
後日届けられた回答書は、責任は全て幕府にあるというもので、首謀者二人は行方不明という、英国側には受け入れられない内容だったため、強硬手段に出る事になり、湾内に潜んでいた薩摩の汽船三隻を拿捕する。このとき、藩命に背いて船を待機させた責任者として切腹が待っているからと下船せず、神奈川で放免された二人が、船長の五代友厚と、通訳で後の外務卿・寺島宗則だった。
この汽船の拿捕を切っ掛けに、薩摩は砲撃を開始する。
アーガス号には110ポンドのアームストロング砲が装備されていた。艦隊の実戦での使用はこれが最初だった。
砲台の破壊にとどまらず鹿児島の街を焼いたことは、後日、英国本国の議会でも問題視された。
英国艦隊が旗艦の艦長・副艦長が砲撃されて戦死し、他に7名の戦死者を出したのにも拘らず、勝敗の決着をつけずに退去したのは、石炭・糧食・弾薬の供給不足が原因と思われるが、薩摩藩はそれを我が方の勝利と喧伝し、幕府も賞賛した。しかし、火砲の優劣は比べようもなく、英国の砲は薩摩砲の射程の4倍もあったし、ロケット砲による火災を含め、薩摩藩の損害は甚大だった。
英軍が上陸しなかったのは、五代らが英軍に問われて、上陸すれば勝ち目はないと言ったからだった。薩摩藩は英軍の上陸を想定して、準備が整っていた。
鹿児島の街を焼いたことは、英国で人道的立場から非難され、文明国の行う戦争ではないと糾弾された。新聞に公文書が公開されていて、当事者個々人の責任が問われた。後の大戦での米軍による無差別爆撃を思うと、当時の英国の世論との違いに、感慨深いものをおぼえる。
元々、英国と一戦交えるなど望んでいなかった薩摩は、軍艦購入を持ち掛け、賠償金を支払うことで急速に英国に接近し、英国を驚かす事になる。生麦事件の実行犯の差し出しや処刑は結局うやむやになった。
オールコックが戻って来て、堅物の代理公使ニールと交代する。サトウはニールに昇進を願い出る。
そんな時期に起きたフランス狙撃兵将校暗殺事件。
「その右腕は、手綱を握ったままの状態で、すこしはなれた場所で発見された。顔の脇が切りおろされており、一ヶ所は鼻をつらぬき、一ヶ所は右の頸静脈を切断し、もう一ヶ所は脊椎をたちわっていた。左腕は、ただ皮一重でぶらさがっており、胴の左わきは、心臓をさらけ出していた。」
「どの切り口も、まったく手ぎわよく、あざやかであった。ということは、このような暗殺者の手に握られた日本刀が、いかに強力な武器であるかを示すものである。」
日本刀で斬り付けられた時の恐ろしさが如実に伝わって来る。
第二次遣欧使節団は、明らかに幕府の時間稼ぎ。
長州藩による米国艦艇砲撃事件の解決に、伊藤俊輔(博文)と井上聞多(馨)2名が尽力したが、結局、藩主の意見を聞くだけに終わり、連合艦隊が下関に向かう。サトウも英軍提督の通訳として乗船。同僚のウィリスは外されたのを悔しがった事が彼の手紙でわかる。サトウの日記に書かれていない分は、このウィリスの手紙に負うところが多い。
艦隊の主力は英国で、次いでフランス、オランダで、日本に開国を迫った米国は砲一門の艦船しか参加していない。これは米国の軍艦が出発直前に故障し、商船に砲一門を移設したためだった。
この頃になると、サトウは日記を一部候文で書いている。
占領された砲台の写真をベアトが撮っている。文章だけよりも、写真の説得力は絶大だ。
休戦協定が結ばれ、長州藩主の批准を待つ間、サトウはベアトを伴って家老の井原主計を訪ねた。写真を撮る為だったがベアトが興味を失って写真は撮られなかった。サトウは井原に伴われて料理屋で食事をするが、アワビ、スイカ、スッポンを食べたが、下関なのにフグは食べなかった。フグが解禁されたのは、伊藤が総理大臣になってからだ。
サトウは横浜へ出航する前に、伊藤俊輔の用意した西洋風の夕食に招かれている。伊藤は翌日にもサトウと出かけていて、急速に親しくなっている。サトウにとっては、倒幕側の人物との人脈がその後、非常に役立つのだが、この時は、伊藤が日本語の堪能なサトウを気に入ったのだろうと思える。
薩英戦争当時、電信はセイロンより東には届いていなかったので、横浜とロンドンの手紙の往復には4ヶ月かかった。本国では軍事行動は慎むようにとの指示を出していたが、郵便事情によって、オールコックの連合艦隊による下関攻撃は、本国のラッセル外相の意向とは全く正反対ものとなってしまった。
p313 サトウは、後年の回想録『一外交官の見た明治維新』の中で、当時の横浜の外国人社会のことを、あるイギリスの外交官は「ヨーロッパの掃き溜め」と呼んだと書いているが、とにかく、ウィリスは、結婚の対象として自分にふさわしい女性に横浜で出会うことが、到底ありえないと、考えていたようである。
*サトウは日本語の読み書きも益々堪能になり、倒幕派の伊藤俊輔(博文)と井上聞多(馨)らに信頼され、親しく交わった。この為、英国は幕府側に援助しつつも、倒幕派の情報も入ってきた。歴史的な場面に通訳として立ち会ったサトウの書き残したものは臨場感に満ちたものになっている。フランスは幕府にぴったり寄り添ったので、やがて横須賀にドックや工廠を造ることになる。
遠い崖 第2巻 薩英戦争
ーアーネスト・サトウ日記抄ー 萩原延壽
生麦事件の賠償金は、紆余曲折の末、英国の要求通りの額が幕府負担分が支払われたが、薩摩藩は依然支払いを引き延ばしていた。交渉のため、7隻の英国艦隊は、横浜から5日掛かって鹿児島に着いた。石炭節約のため大部分を帆走したため。このとき、生麦事件の賠償金の一部は積まれたままだった。
艦隊の砲の総数は、90門だった。
幕府の役人らは艦隊への同乗を断り、幕府の船で英国艦隊の後を追ったのは、薩英の仲介役にでもなるつもりかと思いきや、到着は薩英戦争終了後。大幅に遅れたのは非力な60馬力のエンジンにあるのではなく、幕府内の開国派と攘夷派の板挟みによる折衷案の結果だったらしい。
薩摩は英国との貿易を望んでおり、この交渉をその為に利用する腹積もりがあったが、英国側の賠償要求書にあった事件の首謀者の首を差し出せ、という項目が、責任者(すなわち島津三郎こと久光)の首と幕府側が勝手に解釈した文書が存在した。
鹿児島湾に投錨した旗艦に、薩摩の役人達は小船で何度も来艦し、上陸要請や物資の補給を申し入れたが、英国側に拒絶された。うち、40名程の、回答書を持参した藩の高官と称する一行も乗艦したが、実は生麦事件の当事者2名も加わっており、居合わせた英国公使と艦隊司令官を斬り殺す手筈だった。陸上からの決行の合図を待っていたが、急遽、引き返す事になり、公使らは命拾いしたという。この計画には久光も賛同していた。
後日届けられた回答書は、責任は全て幕府にあるというもので、首謀者二人は行方不明という、英国側には受け入れられない内容だったため、強硬手段に出る事になり、湾内に潜んでいた薩摩の汽船三隻を拿捕する。このとき、藩命に背いて船を待機させた責任者として切腹が待っているからと下船せず、神奈川で放免された二人が、船長の五代友厚と、通訳で後の外務卿・寺島宗則だった。
この汽船の拿捕を切っ掛けに、薩摩は砲撃を開始する。
アーガス号には110ポンドのアームストロング砲が装備されていた。艦隊の実戦での使用はこれが最初だった。
砲台の破壊にとどまらず鹿児島の街を焼いたことは、後日、英国本国の議会でも問題視された。
英国艦隊が旗艦の艦長・副艦長が砲撃されて戦死し、他に7名の戦死者を出したのにも拘らず、勝敗の決着をつけずに退去したのは、石炭・糧食・弾薬の供給不足が原因と思われるが、薩摩藩はそれを我が方の勝利と喧伝し、幕府も賞賛した。しかし、火砲の優劣は比べようもなく、英国の砲は薩摩砲の射程の4倍もあったし、ロケット砲による火災を含め、薩摩藩の損害は甚大だった。
英軍が上陸しなかったのは、五代らが英軍に問われて、上陸すれば勝ち目はないと言ったからだった。薩摩藩は英軍の上陸を想定して、準備が整っていた。
鹿児島の街を焼いたことは、英国で人道的立場から非難され、文明国の行う戦争ではないと糾弾された。新聞に公文書が公開されていて、当事者個々人の責任が問われた。後の大戦での米軍による無差別爆撃を思うと、当時の英国の世論との違いに、感慨深いものをおぼえる。
元々、英国と一戦交えるなど望んでいなかった薩摩は、軍艦購入を持ち掛け、賠償金を支払うことで急速に英国に接近し、英国を驚かす事になる。生麦事件の実行犯の差し出しや処刑は結局うやむやになった。
オールコックが戻って来て、堅物の代理公使ニールと交代する。サトウはニールに昇進を願い出る。
そんな時期に起きたフランス狙撃兵将校暗殺事件。
「その右腕は、手綱を握ったままの状態で、すこしはなれた場所で発見された。顔の脇が切りおろされており、一ヶ所は鼻をつらぬき、一ヶ所は右の頸静脈を切断し、もう一ヶ所は脊椎をたちわっていた。左腕は、ただ皮一重でぶらさがっており、胴の左わきは、心臓をさらけ出していた。」
「どの切り口も、まったく手ぎわよく、あざやかであった。ということは、このような暗殺者の手に握られた日本刀が、いかに強力な武器であるかを示すものである。」
日本刀で斬り付けられた時の恐ろしさが如実に伝わって来る。
第二次遣欧使節団は、明らかに幕府の時間稼ぎ。
長州藩による米国艦艇砲撃事件の解決に、伊藤俊輔(博文)と井上聞多(馨)2名が尽力したが、結局、藩主の意見を聞くだけに終わり、連合艦隊が下関に向かう。サトウも英軍提督の通訳として乗船。同僚のウィリスは外されたのを悔しがった事が彼の手紙でわかる。サトウの日記に書かれていない分は、このウィリスの手紙に負うところが多い。
艦隊の主力は英国で、次いでフランス、オランダで、日本に開国を迫った米国は砲一門の艦船しか参加していない。これは米国の軍艦が出発直前に故障し、商船に砲一門を移設したためだった。
この頃になると、サトウは日記を一部候文で書いている。
占領された砲台の写真をベアトが撮っている。文章だけよりも、写真の説得力は絶大だ。
休戦協定が結ばれ、長州藩主の批准を待つ間、サトウはベアトを伴って家老の井原主計を訪ねた。写真を撮る為だったがベアトが興味を失って写真は撮られなかった。サトウは井原に伴われて料理屋で食事をするが、アワビ、スイカ、スッポンを食べたが、下関なのにフグは食べなかった。フグが解禁されたのは、伊藤が総理大臣になってからだ。
サトウは横浜へ出航する前に、伊藤俊輔の用意した西洋風の夕食に招かれている。伊藤は翌日にもサトウと出かけていて、急速に親しくなっている。サトウにとっては、倒幕側の人物との人脈がその後、非常に役立つのだが、この時は、伊藤が日本語の堪能なサトウを気に入ったのだろうと思える。
薩英戦争当時、電信はセイロンより東には届いていなかったので、横浜とロンドンの手紙の往復には4ヶ月かかった。本国では軍事行動は慎むようにとの指示を出していたが、郵便事情によって、オールコックの連合艦隊による下関攻撃は、本国のラッセル外相の意向とは全く正反対ものとなってしまった。
p313 サトウは、後年の回想録『一外交官の見た明治維新』の中で、当時の横浜の外国人社会のことを、あるイギリスの外交官は「ヨーロッパの掃き溜め」と呼んだと書いているが、とにかく、ウィリスは、結婚の対象として自分にふさわしい女性に横浜で出会うことが、到底ありえないと、考えていたようである。
*サトウは日本語の読み書きも益々堪能になり、倒幕派の伊藤俊輔(博文)と井上聞多(馨)らに信頼され、親しく交わった。この為、英国は幕府側に援助しつつも、倒幕派の情報も入ってきた。歴史的な場面に通訳として立ち会ったサトウの書き残したものは臨場感に満ちたものになっている。フランスは幕府にぴったり寄り添ったので、やがて横須賀にドックや工廠を造ることになる。
進化の教科書 ― 2017年12月14日

読み終えた本
「進化の教科書」全3巻
カール・ジンマー/ダグラス・J・エムレン
ティンバーゲンから、最新の遺伝子レベルの進化論的考察まで。内容は難しいので割愛。(^_^;)
編集する
「進化の教科書」全3巻
カール・ジンマー/ダグラス・J・エムレン
ティンバーゲンから、最新の遺伝子レベルの進化論的考察まで。内容は難しいので割愛。(^_^;)
編集する
読み終えた本 日本紀行 エリザ・R・シドモア ― 2017年04月08日

読み終えた本
日本紀行 /明治の人力車ツァー/ エリザ・R・シドモア
講談社 学術文庫
・エリザ・ルアマー・シドモアは、アメリカの著作家・写真家・地理学者。ナショナルジオグラフィック協会初の女性理事となった。1885年から1928年にかけて度々日本を訪れた親日家であり、日本に関する記事や著作も残している。ワシントンD.C.のポトマック河畔に桜並木を作ることを提案した人物である。 名前のカナ転記については、Elizaに対してエライザやイライザ、Scidmoreに対してシッドモアやスキッドモアなどの表記揺れがある。(Wikipedia)
米国の女性ジャーナリストにより、明治中期の日本が、かなりの日本びいきの目ではあるが,よく描かれている。すでに近代国家の仲間入りをしたとはいえ,まだ江戸時代の名残りが色濃い地方の風景は絶賛している。また,廃仏毀釈で荒廃した寺院や,そのために流出した国宝級の文物を憂いている。E.S.モースの本も読んでおり,同じ時期に,小泉八雲が本を出している。旅行記として,ローウェルの著書も挙がっていた。
p23「東回りコースの船旅では、スエズ運河から長崎沖の手前まで、アジアの民衆は無言のまま腰を下ろし、汚物、ぼろ布、無知、悲惨の中に漬かり、何の不満もなく暮らしているのが目に入ります。不衛生で醜悪な環境にいる中国の民衆、あの濁った河、茫漠とした平原、黄褐色の丘陵を通過し、さらに朝鮮半島のうら淋しい海岸に別れをつげて進みます。
最初に出会う日本は、海岸線から離れた緑の島です。絵のように続く丘陵や頂上に至るまで、その光景はまるで夢の天国です。家並みは玩具に、住民はお人形さんに見えます。その暮らしのさまは清潔で美しく、かつ芸術的で独特の風情があります。」
p66 横須賀の軍艦の描写、浦賀の水飴を詳細に紹介している。
当時、浦賀の名物といえば水飴だったようです。
ネットを検索すると、
http://uragadock.blog104.fc2.com/blog-entry-9.html
更に詳細に研究している人がいます。
http://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-385.html
http://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-386.html
p90-91 ひな祭りの描写 「日本の子供ほど上品で可愛らしい子供はいません。」
p108-109 墨堤、上野の花見。不忍池には周囲に競馬コースがあった。
「ツァーやカイゼルは、ここ東洋の統治者をさぞかし羨ましく思うことでしょう。この国の群衆は何千人が集まっても、爆弾を投げたり、パンや資産の分配で暴動を起こす事はありません。ひたすら桜を愛で賛美し、歌に表すだけが目的なのです。」
p111「向島のカーニバルは、まさに古代ヨーロッパの農神祭です。この春の酒宴は審美的日本人と古代ローマ人との間に大きな類似点を見せ、向島の愛らしい山水庭園を覗けば、花冠の酒神バッカスに出くわすこと請け合いです。男たちは盃や瓢箪を手にし、チュロスのごとく踊ったり、片手を上げて演説したり、一人残らず天性の役者、雄弁家、パントマイム舞踏会に変貌します。でも、へべれけになっても全身から湧き出るのは歓喜と親愛の情だけです。このお祭り騒ぎにとっくみあいの喧嘩もなければ乱暴狼藉もなく、下品な言葉を投げ合う姿もありません。お堅い禁酒家さえ狂気乱舞の酒をあおっているかのように、高笑いの大津波が次から次へと伝播し、道化や扮装がますます滑稽さを帯びて行きます。日が暮れると、吊提灯が茶店や屋台に点り、枝々全体を優美に照らします。夕べの宴では、優雅な身振りで舞妓や芸者の滑らかな舞が演じられ、三味や鼓の音に合わせて果てしなく続きます。夢のような春の宵、舞姫は桜を刺繍した絹衣を装い、簪や花冠を蝶の輪結びの黒髪に輝かせます。やがて雨が降り花びらを散らして、四方に花吹雪が舞って大地は真っ白な絨毯になります。」
p191 イザベラ・バードのガイドを行なった「伊藤」を雇っている。
p318 常に全力で走る人力車夫に向ける視線は優しい
p344 「ベンバント・セリィーニの作品」という表現があったが,ベンヴェヌート・チェッリーニ(Benvenuto Cellini)のことだろう。無理に英語読みにすると分からなくなる。
p348 「陶工は風通しの良い奥まった小部屋で、それぞれ低いろくろと粘土の山を前にし座っています。ある老人が足を曲げて座り、右足は曲げた左膝にしっかり閉じ込め、左足は右腿に上向きに足の裏を置き、どんなブッダ像にも見られぬ信じがたい姿勢をとっています。褌と梟(ふくろう)のような巨大なメガネ以外何も身に付けず、何時間でも好きな姿勢で働くこの禿頭の痩せた老人に、私は本人の作品と同じ位興味がわきました。」
・様々な伝統工芸品が、政府が輸出を奨励したために、非常につまらないものになっていることを作者は嘆いている。
p354「ともあれ、提灯の柔らかな明かりを鑑賞するには、日本で生活するのが一番で、夜毎の惜しみない灯火の利用は、まるでお伽の国のような華麗な効果を生み、それはまさに、紙切れ、幾本もの竹ひご、紙灯芯の周りの植物油から生まれる幻想芸術なのです。」
p358 並河靖之(七宝工芸家。京都生まれ。伝統的有線七宝の作品を発表。また,黒色透明釉を開発し,新境地を拓いた)の工房を訪問
・まだ日本を訪れたことのない米国人を対象にして解説しているので、多少の誤りがあるものの、概ね「分かりやすい」説明になっている。日本人が日本人に説明する文章だとこうはならないだろう。
・当時、ネズミはどこにでもいて、夜中に天井裏を走り回る事は普通だった。京都や奈良の一流ホテルでも、日中にネズミが走り回る事は普通だったようで,著者は、日本人はネズミやハツカネズミに対して敵意がないように見える、と述べている。
p418 「型押し皮革も大阪の重要な製品の1つで、主としてトリエステに輸出され、そこやベニスではポケットブック、書類入れ、名刺、タバコケースが作られ、これらの商品を買うために米国の宝飾店や文房具店は、莫大な大金を払っています。」
p447 「この下関砲撃事件は、日本に対しキリスト教建国の政策を押し付けた恥ずべき外交として、(弱い者いじめ国際年代記)の中で特に目立っています。ともあれ、合衆国は賠償金の分け前を返還し、不正行為に対する消極的陳謝によって、弱者からの略奪と言う恥ずべき行為を遅ればせながら反省しているようです。」
・著者は、京都の大文字焼きや、長崎の精霊流しを驚きながら見ている。
・シドモア女史の兄は、グラント大統領の側近で明治14年に横浜領事館の書記生に就任。明治17年には大阪副領事に就任している。明治18年には神奈川県の領事館の副総領事兼総領事代理に就任、明治24年まで在任。後。横浜総領事となり、大正11年、横浜山手246番の自宅で死去。
・妹であるシドモア女史は、明治23年ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティーに入会、その後初の女性理事として活躍することとなる。
・大正13年のアメリカ排日移民法に抗議し翌年ジュネーブに移住。昭和3年11月3日、明治節の日にジュネーブの自宅で永眠。
日本紀行 /明治の人力車ツァー/ エリザ・R・シドモア
講談社 学術文庫
・エリザ・ルアマー・シドモアは、アメリカの著作家・写真家・地理学者。ナショナルジオグラフィック協会初の女性理事となった。1885年から1928年にかけて度々日本を訪れた親日家であり、日本に関する記事や著作も残している。ワシントンD.C.のポトマック河畔に桜並木を作ることを提案した人物である。 名前のカナ転記については、Elizaに対してエライザやイライザ、Scidmoreに対してシッドモアやスキッドモアなどの表記揺れがある。(Wikipedia)
米国の女性ジャーナリストにより、明治中期の日本が、かなりの日本びいきの目ではあるが,よく描かれている。すでに近代国家の仲間入りをしたとはいえ,まだ江戸時代の名残りが色濃い地方の風景は絶賛している。また,廃仏毀釈で荒廃した寺院や,そのために流出した国宝級の文物を憂いている。E.S.モースの本も読んでおり,同じ時期に,小泉八雲が本を出している。旅行記として,ローウェルの著書も挙がっていた。
p23「東回りコースの船旅では、スエズ運河から長崎沖の手前まで、アジアの民衆は無言のまま腰を下ろし、汚物、ぼろ布、無知、悲惨の中に漬かり、何の不満もなく暮らしているのが目に入ります。不衛生で醜悪な環境にいる中国の民衆、あの濁った河、茫漠とした平原、黄褐色の丘陵を通過し、さらに朝鮮半島のうら淋しい海岸に別れをつげて進みます。
最初に出会う日本は、海岸線から離れた緑の島です。絵のように続く丘陵や頂上に至るまで、その光景はまるで夢の天国です。家並みは玩具に、住民はお人形さんに見えます。その暮らしのさまは清潔で美しく、かつ芸術的で独特の風情があります。」
p66 横須賀の軍艦の描写、浦賀の水飴を詳細に紹介している。
当時、浦賀の名物といえば水飴だったようです。
ネットを検索すると、
http://uragadock.blog104.fc2.com/blog-entry-9.html
更に詳細に研究している人がいます。
http://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-385.html
http://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-386.html
p90-91 ひな祭りの描写 「日本の子供ほど上品で可愛らしい子供はいません。」
p108-109 墨堤、上野の花見。不忍池には周囲に競馬コースがあった。
「ツァーやカイゼルは、ここ東洋の統治者をさぞかし羨ましく思うことでしょう。この国の群衆は何千人が集まっても、爆弾を投げたり、パンや資産の分配で暴動を起こす事はありません。ひたすら桜を愛で賛美し、歌に表すだけが目的なのです。」
p111「向島のカーニバルは、まさに古代ヨーロッパの農神祭です。この春の酒宴は審美的日本人と古代ローマ人との間に大きな類似点を見せ、向島の愛らしい山水庭園を覗けば、花冠の酒神バッカスに出くわすこと請け合いです。男たちは盃や瓢箪を手にし、チュロスのごとく踊ったり、片手を上げて演説したり、一人残らず天性の役者、雄弁家、パントマイム舞踏会に変貌します。でも、へべれけになっても全身から湧き出るのは歓喜と親愛の情だけです。このお祭り騒ぎにとっくみあいの喧嘩もなければ乱暴狼藉もなく、下品な言葉を投げ合う姿もありません。お堅い禁酒家さえ狂気乱舞の酒をあおっているかのように、高笑いの大津波が次から次へと伝播し、道化や扮装がますます滑稽さを帯びて行きます。日が暮れると、吊提灯が茶店や屋台に点り、枝々全体を優美に照らします。夕べの宴では、優雅な身振りで舞妓や芸者の滑らかな舞が演じられ、三味や鼓の音に合わせて果てしなく続きます。夢のような春の宵、舞姫は桜を刺繍した絹衣を装い、簪や花冠を蝶の輪結びの黒髪に輝かせます。やがて雨が降り花びらを散らして、四方に花吹雪が舞って大地は真っ白な絨毯になります。」
p191 イザベラ・バードのガイドを行なった「伊藤」を雇っている。
p318 常に全力で走る人力車夫に向ける視線は優しい
p344 「ベンバント・セリィーニの作品」という表現があったが,ベンヴェヌート・チェッリーニ(Benvenuto Cellini)のことだろう。無理に英語読みにすると分からなくなる。
p348 「陶工は風通しの良い奥まった小部屋で、それぞれ低いろくろと粘土の山を前にし座っています。ある老人が足を曲げて座り、右足は曲げた左膝にしっかり閉じ込め、左足は右腿に上向きに足の裏を置き、どんなブッダ像にも見られぬ信じがたい姿勢をとっています。褌と梟(ふくろう)のような巨大なメガネ以外何も身に付けず、何時間でも好きな姿勢で働くこの禿頭の痩せた老人に、私は本人の作品と同じ位興味がわきました。」
・様々な伝統工芸品が、政府が輸出を奨励したために、非常につまらないものになっていることを作者は嘆いている。
p354「ともあれ、提灯の柔らかな明かりを鑑賞するには、日本で生活するのが一番で、夜毎の惜しみない灯火の利用は、まるでお伽の国のような華麗な効果を生み、それはまさに、紙切れ、幾本もの竹ひご、紙灯芯の周りの植物油から生まれる幻想芸術なのです。」
p358 並河靖之(七宝工芸家。京都生まれ。伝統的有線七宝の作品を発表。また,黒色透明釉を開発し,新境地を拓いた)の工房を訪問
・まだ日本を訪れたことのない米国人を対象にして解説しているので、多少の誤りがあるものの、概ね「分かりやすい」説明になっている。日本人が日本人に説明する文章だとこうはならないだろう。
・当時、ネズミはどこにでもいて、夜中に天井裏を走り回る事は普通だった。京都や奈良の一流ホテルでも、日中にネズミが走り回る事は普通だったようで,著者は、日本人はネズミやハツカネズミに対して敵意がないように見える、と述べている。
p418 「型押し皮革も大阪の重要な製品の1つで、主としてトリエステに輸出され、そこやベニスではポケットブック、書類入れ、名刺、タバコケースが作られ、これらの商品を買うために米国の宝飾店や文房具店は、莫大な大金を払っています。」
p447 「この下関砲撃事件は、日本に対しキリスト教建国の政策を押し付けた恥ずべき外交として、(弱い者いじめ国際年代記)の中で特に目立っています。ともあれ、合衆国は賠償金の分け前を返還し、不正行為に対する消極的陳謝によって、弱者からの略奪と言う恥ずべき行為を遅ればせながら反省しているようです。」
・著者は、京都の大文字焼きや、長崎の精霊流しを驚きながら見ている。
・シドモア女史の兄は、グラント大統領の側近で明治14年に横浜領事館の書記生に就任。明治17年には大阪副領事に就任している。明治18年には神奈川県の領事館の副総領事兼総領事代理に就任、明治24年まで在任。後。横浜総領事となり、大正11年、横浜山手246番の自宅で死去。
・妹であるシドモア女史は、明治23年ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティーに入会、その後初の女性理事として活躍することとなる。
・大正13年のアメリカ排日移民法に抗議し翌年ジュネーブに移住。昭和3年11月3日、明治節の日にジュネーブの自宅で永眠。
鳥学大全 ― 2017年01月30日

読んでいた本
鳥学大全 東京大学出版会(序文で秋篠宮は,とりがく大全と読むようにとのこと。鳥学「ちょうがく」と読むほどのものではないということか。)
---amazon.co.jpから
内容紹介
山階鳥類研究所の標本・関連文献などの鳥類コレクションをはじめて広く社会に公開する。同研究所所蔵の鳥類標本を解説したばかりでなく、鳥のさまざまな事象について、秋篠宮文仁殿下、黒田清子さん、荒俣 宏さんをはじめとした40人の執筆者が多方面から言及し、鳥学の楽しさを伝える。【カラー口絵64頁】
—-
鳥類図譜の系譜 荒俣宏
天の岩戸神話で、天照女神が岩戸に身を隠した時に鳴いたニワトリ(常世長鳴鳥)を飼っていた「土師」氏(はじし)は、墓造りの有力豪族だった。で,さっそく、件の辞書で検索すると、
---
①(「はにし(土師)」の変化した語) 埴輪などの土器を作ることをつかさどった人。土師部を統轄して土器を貢納した伴部とものみやつこ。令制では諸陵司の伴部となり、陵戸を管して凶礼をつかさどった。のち、菅原氏と称して、同族は多く畿内に住み、秋篠・大枝などの諸氏を分立した。土師人はしうど。(伴部は部下のこと、陵戸は、みささぎべ、で天皇の墓を守る人のこと)
---
オーデュボンの「アメリカの鳥類」は、ペリーに依って日本にやってきたが、現物は行方不明。
鶏の家禽化 秋篠宮文仁
鶏の祖先種は赤色野鶏だろうとダーウィンも言っていたが、ミトコンドリアDNAからそれが裏付けられた。それも、タイやその近隣地域由来であろう、とのこと。
最も古い鶏の骨は、モエンジョ=ダーロよりも古い、紀元前6000年の中国湖南省・湖北省の遺跡から出土している、としているが、今後の核DNA解析などで、他の可能性も否定していない。
*養鶏の目的の一つ、「報晨」が、件の辞書には無い。残念。
「鳥の人」ジョン・グールドと『ハチドリ科鳥類図譜』 黒田清子
オーデュボンではなく、英国人のグールドを取り上げたことは、戦前からの英国王室との深いつながりがあるためだろう。
*グールドについては、以前小文を書いたことがあった。
http://www.asahi-net.or.jp/~fv9h-ab/kamakura/essay.html#Anchor182862
この本に黒田さんが詳しく書かれているので、勉強になる。
グールドは幼少期に庭師であった父の影響で色鮮やかな鳥の卵や鳥そのものに興味を抱き、やがて剥製の技術を身に付ける。その過程で、鳥の詳細なスケッチが自然と身に付いたのではとの話を紹介している。グールド23歳の時、ロンドンの博物館学芸員に任ぜられ、英国のセルビー、ライデン博物館のテミンク、米国のオーデュボン等の知己を得ることになる。
ハチドリの図譜では金属光沢を出すのに、金箔の上に透明なオイルとニスの混合物を塗るというものだった。
1837年、ビーグル号で戻ったダーウィンから、図版作成を依頼されている。この時、二人は嘴の大きさが異なるフィンチに関心を持った。
「鳥の人:the Bird Man」は彼の墓碑に刻まれている。
*恐竜はいつどのようにして鳥になったか 真鍋真
も読んだ。
631ページもあるので、二週間では読めなかった。川崎の図書館から借りているので、一旦返さなければならない。又、予約しておこう。他の市から借りた本も、他に予約がなければ、窓口で返却を確認してから、継続できれば良いのだが。一度、川崎の図書館に戻してからでないと、再度借りられないのは不便だ。
*皇族や王族が学者・研究者という国はどれくらいあるのだろうか。グスタフ6世アドルフ (スウェーデン王) は植物学および考古学の専門家だそうだが,他に日本ほどのところがどれほどあるのだろうか,知りたいものだ。
鳥学大全 東京大学出版会(序文で秋篠宮は,とりがく大全と読むようにとのこと。鳥学「ちょうがく」と読むほどのものではないということか。)
---amazon.co.jpから
内容紹介
山階鳥類研究所の標本・関連文献などの鳥類コレクションをはじめて広く社会に公開する。同研究所所蔵の鳥類標本を解説したばかりでなく、鳥のさまざまな事象について、秋篠宮文仁殿下、黒田清子さん、荒俣 宏さんをはじめとした40人の執筆者が多方面から言及し、鳥学の楽しさを伝える。【カラー口絵64頁】
—-
鳥類図譜の系譜 荒俣宏
天の岩戸神話で、天照女神が岩戸に身を隠した時に鳴いたニワトリ(常世長鳴鳥)を飼っていた「土師」氏(はじし)は、墓造りの有力豪族だった。で,さっそく、件の辞書で検索すると、
---
①(「はにし(土師)」の変化した語) 埴輪などの土器を作ることをつかさどった人。土師部を統轄して土器を貢納した伴部とものみやつこ。令制では諸陵司の伴部となり、陵戸を管して凶礼をつかさどった。のち、菅原氏と称して、同族は多く畿内に住み、秋篠・大枝などの諸氏を分立した。土師人はしうど。(伴部は部下のこと、陵戸は、みささぎべ、で天皇の墓を守る人のこと)
---
オーデュボンの「アメリカの鳥類」は、ペリーに依って日本にやってきたが、現物は行方不明。
鶏の家禽化 秋篠宮文仁
鶏の祖先種は赤色野鶏だろうとダーウィンも言っていたが、ミトコンドリアDNAからそれが裏付けられた。それも、タイやその近隣地域由来であろう、とのこと。
最も古い鶏の骨は、モエンジョ=ダーロよりも古い、紀元前6000年の中国湖南省・湖北省の遺跡から出土している、としているが、今後の核DNA解析などで、他の可能性も否定していない。
*養鶏の目的の一つ、「報晨」が、件の辞書には無い。残念。
「鳥の人」ジョン・グールドと『ハチドリ科鳥類図譜』 黒田清子
オーデュボンではなく、英国人のグールドを取り上げたことは、戦前からの英国王室との深いつながりがあるためだろう。
*グールドについては、以前小文を書いたことがあった。
http://www.asahi-net.or.jp/~fv9h-ab/kamakura/essay.html#Anchor182862
この本に黒田さんが詳しく書かれているので、勉強になる。
グールドは幼少期に庭師であった父の影響で色鮮やかな鳥の卵や鳥そのものに興味を抱き、やがて剥製の技術を身に付ける。その過程で、鳥の詳細なスケッチが自然と身に付いたのではとの話を紹介している。グールド23歳の時、ロンドンの博物館学芸員に任ぜられ、英国のセルビー、ライデン博物館のテミンク、米国のオーデュボン等の知己を得ることになる。
ハチドリの図譜では金属光沢を出すのに、金箔の上に透明なオイルとニスの混合物を塗るというものだった。
1837年、ビーグル号で戻ったダーウィンから、図版作成を依頼されている。この時、二人は嘴の大きさが異なるフィンチに関心を持った。
「鳥の人:the Bird Man」は彼の墓碑に刻まれている。
*恐竜はいつどのようにして鳥になったか 真鍋真
も読んだ。
631ページもあるので、二週間では読めなかった。川崎の図書館から借りているので、一旦返さなければならない。又、予約しておこう。他の市から借りた本も、他に予約がなければ、窓口で返却を確認してから、継続できれば良いのだが。一度、川崎の図書館に戻してからでないと、再度借りられないのは不便だ。
*皇族や王族が学者・研究者という国はどれくらいあるのだろうか。グスタフ6世アドルフ (スウェーデン王) は植物学および考古学の専門家だそうだが,他に日本ほどのところがどれほどあるのだろうか,知りたいものだ。
「カルト村で生まれました」 高田かや著 文藝春秋 ― 2017年01月24日

娘が借りていた本を図書館に返しに行くのだけど,昨晩預かった本の中に漫画が一冊あったので,読み終えた。
「カルト村で生まれました」 高田かや著 文藝春秋
———Amazonから
内容紹介
「平成の話とは思えない!」「こんな村があるなんて!」と、WEB連載時から大反響!!
衝撃的な初投稿作品が単行本に!
「所有のない社会」を目指す「カルト村」で生まれ、19歳のときに自分の意志で村を出た著者が、両親と離され、労働、空腹、体罰が当たり前の暮らしを送っていた少女時代を回想して描いた「実録コミックエッセイ」。
〈カルト村ってどんなとこ?〉
●大人と子供の生活空間が別々 ●朝5時半起床で労働 ●布団は2人で1組
●食事は昼と夜のみ ●卵ミルクを飲ませられる ●お小遣いはもらえない
●すべてのモノが共有で、服もお下がり ●男子は丸刈り、女子はショートカット
●ビンタ、正座、食事抜きなど体罰は当たり前 ●手紙は検閲される
●テレビは「日本昔ばなし」のみ ●漫画は禁止、ペットも飼えない
●自然はいっぱい。探険など外遊びは楽しい♪
内容(「BOOK」データベースより)
WEB連載時から大反響!!「所有のない社会」を目指すカルト村で生まれ、両親と離され、労働、空腹、体罰が当たり前の暮らしを送っていた少女時代を描く「実録コミックエッセイ」
——ここまで
ヤマギシ会だろう。社宅に住んでいた時は,ヤマギシから卵とか買っていたように記憶している。ミカンは緑健だったかな?そういうのが流行った時代だった。
テレビでも紹介されたことがあった。私有財産は禁止。お小遣いもなし。下着も上着も全部共用。外出時はおしゃれ着も借りて着られるし,お小遣いも渡されるが,消え物しか買えない。その時も驚いたが,最近までそうだったようだ。原始共産制とでも言うのだろうか。筆者が村を出る時は,まるで北朝鮮の人がソウルにでも来たような雰囲気。子供に年中無休・無給で労働させるということは問題になったことも書かれている。生まれた時から「村」で育つと,疑問に思わないかもしれないのが怖い。筆者のように,大人になれば,村から出ることは自由らしい。筆者は戻る気は無いようだ。
「カルト村で生まれました」 高田かや著 文藝春秋
———Amazonから
内容紹介
「平成の話とは思えない!」「こんな村があるなんて!」と、WEB連載時から大反響!!
衝撃的な初投稿作品が単行本に!
「所有のない社会」を目指す「カルト村」で生まれ、19歳のときに自分の意志で村を出た著者が、両親と離され、労働、空腹、体罰が当たり前の暮らしを送っていた少女時代を回想して描いた「実録コミックエッセイ」。
〈カルト村ってどんなとこ?〉
●大人と子供の生活空間が別々 ●朝5時半起床で労働 ●布団は2人で1組
●食事は昼と夜のみ ●卵ミルクを飲ませられる ●お小遣いはもらえない
●すべてのモノが共有で、服もお下がり ●男子は丸刈り、女子はショートカット
●ビンタ、正座、食事抜きなど体罰は当たり前 ●手紙は検閲される
●テレビは「日本昔ばなし」のみ ●漫画は禁止、ペットも飼えない
●自然はいっぱい。探険など外遊びは楽しい♪
内容(「BOOK」データベースより)
WEB連載時から大反響!!「所有のない社会」を目指すカルト村で生まれ、両親と離され、労働、空腹、体罰が当たり前の暮らしを送っていた少女時代を描く「実録コミックエッセイ」
——ここまで
ヤマギシ会だろう。社宅に住んでいた時は,ヤマギシから卵とか買っていたように記憶している。ミカンは緑健だったかな?そういうのが流行った時代だった。
テレビでも紹介されたことがあった。私有財産は禁止。お小遣いもなし。下着も上着も全部共用。外出時はおしゃれ着も借りて着られるし,お小遣いも渡されるが,消え物しか買えない。その時も驚いたが,最近までそうだったようだ。原始共産制とでも言うのだろうか。筆者が村を出る時は,まるで北朝鮮の人がソウルにでも来たような雰囲気。子供に年中無休・無給で労働させるということは問題になったことも書かれている。生まれた時から「村」で育つと,疑問に思わないかもしれないのが怖い。筆者のように,大人になれば,村から出ることは自由らしい。筆者は戻る気は無いようだ。
読み終えた本 NOTO -能登・人に知られぬ日本の辺境- パーシヴァル・ローウェル著 ― 2016年12月28日
読み終えた本
NOTO -能登・人に知られぬ日本の辺境- パーシヴァル・ローウェル著
AN UNEXPLORED CORNER OF JAPAN
十月社 1991年
(本書ではローエルだがローウェルとした:昔からローウェルって言っていたし,辞典でもローウェルなので・・)
ローウェルについて
Percival Lowell (1855—1916)
アメリカの天文学者。ボストンの資産家の子として生まれる。ハーバード大学で数学を修め、1876年に卒業。祖父の綿業関係の仕事で1年間ヨーロッパに旅行したのち、実業界で活躍した。東洋への興味から、1883〜93年(明治16〜26)外交官の資格で日本に滞在し、日本の人情・習慣・ことばなどを研究し、また朝鮮にも旅行するなどして、紀行文や印象記を4冊著したが、なかでも『能登(ノト)』(1891)は日本の民俗をよく記している。小学校時代から天文学への興味をもっていたが、93年、日本から帰国すると私財をもって天文台の建設にとりかかり、翌年、アリゾナ州フラグスタッフ(標高2200メートル)に45.7センチメートルおよび30.5センチメートルの望遠鏡を設置した天文台を完成、96年には61センチメートル望遠鏡も備えた。彼はまず火星表面の観測に着手した。1877年の火星大接近の際、イタリアのスキャパレリが火星表面に「カナリ」(水路)を発見していたが、ローウェルはこれを人工構造物とみなし、技術をもった生物の存在を仮想し、その検証に熱意を注いだ。彼の火星に関する知見は1903年までに3冊の著作、1枚の写真としてまとめられ、広く普及した。また16年に『惑星の発生』を著し、天王星の摂動にかかわる天体は海王星だけでなく、ほかにもう一つの未知の惑星があることを予想した。この惑星は彼の死後1930年にトンボーによって発見され、冥王星と名づけられた。〈島村福太郎〉電子ブック版『日本大百科全書』
・気になったところのメモ
p44 ボーイ兼コックの山田栄次郎という青年を雇う。
沢山の缶詰、手製のパン、ウィスキー1本、ビール少々を携えて旅立つ。横浜のビールを褒めていて、日本でも宴会で飲むようになっていると述べている。
上野から高崎へ。5分遅刻したため列車に乗せてもらえず、3時間後に出発。高崎で一泊している。宿で出た缶詰の加糖練乳にうんざり。
ローウェルには、極東に関する四冊の著書があり、小泉八雲は三番目の著書「極東の心」を読んで来日を決意した。
ローウェルは能登での写真を撮ったはずなのに、初版本には写真が一枚も無かったため、訳者がローウェル天文台を調べてもらい、多数のネガは発見された。
日本と朝鮮に行っているのは、イザベラ・バードと同じだが、あとがきに依れば、旅行では無く、米国公使館の通達により、朝鮮李朝からワシントンへの外交使節団の随員としてだった。ローウェルは再三受諾を拒んだ末だった。帰国後、朝鮮には3ヶ月滞在した。
その後、ローウェルと共に渡米した使節団のメンバーが京城でクーデターを起こし、清国軍と日本軍との戦闘で、日本公使館が焼き討ちに会い、在留民婦女子が暴行、或いは殺害された。(甲甲の変 1884年12月)
p61 ロボットのようにという記述 いつからロボットという言葉があるのか?
*調べてみたらやはり「ロボット(robot)という語は、1920年にチェコスロバキア(当時)の小説家カレル・チャペックが発表した戯曲『R.U.R.(ロッサム万能ロボット商会)』において初めて用いられた。」Wikipedia というわけで,ローウェルの時代にはなかったので,訳者が意訳で使ったのだろう。
和倉温泉に最初に来た外国人はローウェルでは無く、二人の欧州人だった。
p130 人力車夫は25マイルも小休止するだけで走った者がいる。
p139 ローウェルは異教徒の信仰に敬意を込めて感動している。 針ノ木峠への道。山開き前のため難儀した様子が痛々しい。
立山下(りゅうざんした)から有峰へ、雪渓を案内人を雇って登る。一行が山小屋に到着する1日前に、樵が一人転落死している。
p181 コウモリ傘を紛失。遺失物の届けを出す。海外からの郵便を受け取る。
p185 奇妙な鳥の声の記述。ヒヨドリか?
p187 天竜下りの後、移動のために船頭を雇おうとするが、誰も相手にしてくれず,警官を呼んだが、パスポートの期限切れを見破られる。警官はどうせ東京に戻るのだからと強制送還はしなかった。
天竜下りでは、勝手に荷物を積まれたりしたが、途中で降ろさせたり、舟に乗れずに難儀している商人二人を乗船させ、料金は受け取らないなど。
天竜川には東海道線の鉄橋が掛かっている。
・あとがきから
同郷の親友、ビゲロー(ボストン美術館の日本美術部の基礎を作った)の後を追って来日した。
小泉八雲が来日したのは、ローウェルの七年後。
碓氷峠はまだアプト式鉄道が無く、鉄道馬車だった。
遅刻して乗り損ね、歩く羽目に。軽井沢を紹介したアレクサンダー・クロフト・ショーはローウェルの前年に軽井沢に来ている。上田城も車中から見ていおり、失われた武家社会を惜しむかの様な詩を詠んでいる。
何故能登に行きたかったのかといえば、地図を漠然と眺めている時に、その奇妙に曲がった形からだった。
ローウェルは学者一家に生まれたが、妹は著名な詩人であったこともあるのか、文才に長けており、学者らしからぬ筆致で紀行文をものしている。
能登旅行の前に 今の中央大学で講演し「劣悪なる欧米人になるなかれ、優秀なる日本人たれ!」と若い学生たちに述べた。
p223 「他の人たちがなんと述べようとも,私は日本人が地球の上での,最も幸せな民族の一つだと言いたく,それは彼らに接すると,こちらの心が非常に魅きつけられる事実でも明らかだ。」
NOTO -能登・人に知られぬ日本の辺境- パーシヴァル・ローウェル著
AN UNEXPLORED CORNER OF JAPAN
十月社 1991年
(本書ではローエルだがローウェルとした:昔からローウェルって言っていたし,辞典でもローウェルなので・・)
ローウェルについて
Percival Lowell (1855—1916)
アメリカの天文学者。ボストンの資産家の子として生まれる。ハーバード大学で数学を修め、1876年に卒業。祖父の綿業関係の仕事で1年間ヨーロッパに旅行したのち、実業界で活躍した。東洋への興味から、1883〜93年(明治16〜26)外交官の資格で日本に滞在し、日本の人情・習慣・ことばなどを研究し、また朝鮮にも旅行するなどして、紀行文や印象記を4冊著したが、なかでも『能登(ノト)』(1891)は日本の民俗をよく記している。小学校時代から天文学への興味をもっていたが、93年、日本から帰国すると私財をもって天文台の建設にとりかかり、翌年、アリゾナ州フラグスタッフ(標高2200メートル)に45.7センチメートルおよび30.5センチメートルの望遠鏡を設置した天文台を完成、96年には61センチメートル望遠鏡も備えた。彼はまず火星表面の観測に着手した。1877年の火星大接近の際、イタリアのスキャパレリが火星表面に「カナリ」(水路)を発見していたが、ローウェルはこれを人工構造物とみなし、技術をもった生物の存在を仮想し、その検証に熱意を注いだ。彼の火星に関する知見は1903年までに3冊の著作、1枚の写真としてまとめられ、広く普及した。また16年に『惑星の発生』を著し、天王星の摂動にかかわる天体は海王星だけでなく、ほかにもう一つの未知の惑星があることを予想した。この惑星は彼の死後1930年にトンボーによって発見され、冥王星と名づけられた。〈島村福太郎〉電子ブック版『日本大百科全書』
・気になったところのメモ
p44 ボーイ兼コックの山田栄次郎という青年を雇う。
沢山の缶詰、手製のパン、ウィスキー1本、ビール少々を携えて旅立つ。横浜のビールを褒めていて、日本でも宴会で飲むようになっていると述べている。
上野から高崎へ。5分遅刻したため列車に乗せてもらえず、3時間後に出発。高崎で一泊している。宿で出た缶詰の加糖練乳にうんざり。
ローウェルには、極東に関する四冊の著書があり、小泉八雲は三番目の著書「極東の心」を読んで来日を決意した。
ローウェルは能登での写真を撮ったはずなのに、初版本には写真が一枚も無かったため、訳者がローウェル天文台を調べてもらい、多数のネガは発見された。
日本と朝鮮に行っているのは、イザベラ・バードと同じだが、あとがきに依れば、旅行では無く、米国公使館の通達により、朝鮮李朝からワシントンへの外交使節団の随員としてだった。ローウェルは再三受諾を拒んだ末だった。帰国後、朝鮮には3ヶ月滞在した。
その後、ローウェルと共に渡米した使節団のメンバーが京城でクーデターを起こし、清国軍と日本軍との戦闘で、日本公使館が焼き討ちに会い、在留民婦女子が暴行、或いは殺害された。(甲甲の変 1884年12月)
p61 ロボットのようにという記述 いつからロボットという言葉があるのか?
*調べてみたらやはり「ロボット(robot)という語は、1920年にチェコスロバキア(当時)の小説家カレル・チャペックが発表した戯曲『R.U.R.(ロッサム万能ロボット商会)』において初めて用いられた。」Wikipedia というわけで,ローウェルの時代にはなかったので,訳者が意訳で使ったのだろう。
和倉温泉に最初に来た外国人はローウェルでは無く、二人の欧州人だった。
p130 人力車夫は25マイルも小休止するだけで走った者がいる。
p139 ローウェルは異教徒の信仰に敬意を込めて感動している。 針ノ木峠への道。山開き前のため難儀した様子が痛々しい。
立山下(りゅうざんした)から有峰へ、雪渓を案内人を雇って登る。一行が山小屋に到着する1日前に、樵が一人転落死している。
p181 コウモリ傘を紛失。遺失物の届けを出す。海外からの郵便を受け取る。
p185 奇妙な鳥の声の記述。ヒヨドリか?
p187 天竜下りの後、移動のために船頭を雇おうとするが、誰も相手にしてくれず,警官を呼んだが、パスポートの期限切れを見破られる。警官はどうせ東京に戻るのだからと強制送還はしなかった。
天竜下りでは、勝手に荷物を積まれたりしたが、途中で降ろさせたり、舟に乗れずに難儀している商人二人を乗船させ、料金は受け取らないなど。
天竜川には東海道線の鉄橋が掛かっている。
・あとがきから
同郷の親友、ビゲロー(ボストン美術館の日本美術部の基礎を作った)の後を追って来日した。
小泉八雲が来日したのは、ローウェルの七年後。
碓氷峠はまだアプト式鉄道が無く、鉄道馬車だった。
遅刻して乗り損ね、歩く羽目に。軽井沢を紹介したアレクサンダー・クロフト・ショーはローウェルの前年に軽井沢に来ている。上田城も車中から見ていおり、失われた武家社会を惜しむかの様な詩を詠んでいる。
何故能登に行きたかったのかといえば、地図を漠然と眺めている時に、その奇妙に曲がった形からだった。
ローウェルは学者一家に生まれたが、妹は著名な詩人であったこともあるのか、文才に長けており、学者らしからぬ筆致で紀行文をものしている。
能登旅行の前に 今の中央大学で講演し「劣悪なる欧米人になるなかれ、優秀なる日本人たれ!」と若い学生たちに述べた。
p223 「他の人たちがなんと述べようとも,私は日本人が地球の上での,最も幸せな民族の一つだと言いたく,それは彼らに接すると,こちらの心が非常に魅きつけられる事実でも明らかだ。」
読み終えた本「素数ゼミの謎」 ― 2016年07月25日
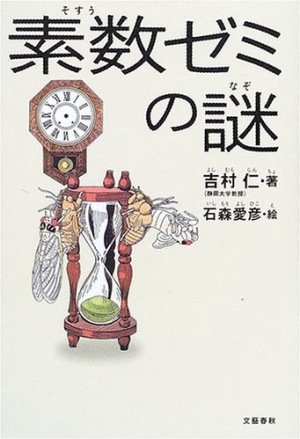
読み終えた本「素数ゼミの謎」吉村 仁著 文藝春秋
米国には13年(4種)と17年(3種)毎に大発生するセミが知られている。
このセミが,なぜ「素数」の発生周期を持つかを,数学的に説明した。
吉村以前に,素数年による周期発生の意味として,捕食者との同期を避けるためと言われていたが,吉村は,氷河期がセミの生息範囲を狭め,近親交配を繰り返す結果,周期がわずかに違う交雑種が生まれていくとした。そうすると,ずれた時期に発生した個体は交配する相手がいないため,これが積み重なると,種の滅亡へとつながる。そこで,13と17という素数の発生年が,必要最小の交雑を防ぐ数だったのではというものです。この2数の最小公倍数は素数同士なので221年となる。
しかし,疑問も残る。13年ゼミと17年ゼミが交雑して15年ゼミができるのかということが確認されていない。米国には周期ゼミ以外に100種ものセミが生息しているが,それらは素数の発生周期ではなくても,種を存続させている。
これは私見だが,偶然(というか,当初はそれなりの生態学的な,そして数学的な意味があり),素数の発生年を持ってしまったため,もうそこから這い出ることのできない穴にはまってしまったセミなのではないかと思うのです。
少し考えてみました。
北米以外に周期ゼミがいない理由。これは吉村先生のいう通り,氷河期のためで,発生周期が13年以上と長くなった。日本のセミは毎年発生するが,1933年,東北大学の佐藤隼夫さんが仙台の大学構内で,金網で囲った飼育室を作り,アブラゼミとミンミンゼミを多数放した。そうしたところ,7年目にアブラゼミとミンミンゼミの成虫がそれぞれ見つかった。アロエでツクツクボウシを飼育した例では,翌年に成虫が出てきたそうで,発生の周期は条件によって様々なようだ。
*「月刊たくさんのふしぎ:宮武頼夫著」福音館書店1987年
*日本で周期ゼミが発生しないのは,氷河期がなかったから,素数年の発生がなかったためだろう。
参考:
http://wired.jp/2009/05/25/13年か17年で大発生するセミ:謎を日本の研究者ら/
17年ゼミの発生の様子
https://www.youtube.com/watch?v=rXlIeUmqrpk
米国には13年(4種)と17年(3種)毎に大発生するセミが知られている。
このセミが,なぜ「素数」の発生周期を持つかを,数学的に説明した。
吉村以前に,素数年による周期発生の意味として,捕食者との同期を避けるためと言われていたが,吉村は,氷河期がセミの生息範囲を狭め,近親交配を繰り返す結果,周期がわずかに違う交雑種が生まれていくとした。そうすると,ずれた時期に発生した個体は交配する相手がいないため,これが積み重なると,種の滅亡へとつながる。そこで,13と17という素数の発生年が,必要最小の交雑を防ぐ数だったのではというものです。この2数の最小公倍数は素数同士なので221年となる。
しかし,疑問も残る。13年ゼミと17年ゼミが交雑して15年ゼミができるのかということが確認されていない。米国には周期ゼミ以外に100種ものセミが生息しているが,それらは素数の発生周期ではなくても,種を存続させている。
これは私見だが,偶然(というか,当初はそれなりの生態学的な,そして数学的な意味があり),素数の発生年を持ってしまったため,もうそこから這い出ることのできない穴にはまってしまったセミなのではないかと思うのです。
少し考えてみました。
北米以外に周期ゼミがいない理由。これは吉村先生のいう通り,氷河期のためで,発生周期が13年以上と長くなった。日本のセミは毎年発生するが,1933年,東北大学の佐藤隼夫さんが仙台の大学構内で,金網で囲った飼育室を作り,アブラゼミとミンミンゼミを多数放した。そうしたところ,7年目にアブラゼミとミンミンゼミの成虫がそれぞれ見つかった。アロエでツクツクボウシを飼育した例では,翌年に成虫が出てきたそうで,発生の周期は条件によって様々なようだ。
*「月刊たくさんのふしぎ:宮武頼夫著」福音館書店1987年
*日本で周期ゼミが発生しないのは,氷河期がなかったから,素数年の発生がなかったためだろう。
参考:
http://wired.jp/2009/05/25/13年か17年で大発生するセミ:謎を日本の研究者ら/
17年ゼミの発生の様子
https://www.youtube.com/watch?v=rXlIeUmqrpk
読み終えた本「天才たちの日課」 ― 2016年06月24日

読み終えた本「天才たちの日課」メイソン・カリー著
原題「DAILY RITUALS:How Artists Work」
フィルムアート社 (2014/12/15)
近・現代の作家、芸術家,音楽家,思想家,医師,科学者などの日常、1日の過ごし方を調べたもので,原題にもある通り,天才だけを取り上げたものではない。
これらの人たちは,創作することを苦悩とする場合もあり,楽しんでいる人もいる。午前中から午後にかけて集中して著述に励む人と,深夜という人も多い。普段は普通の主婦で,家人が寝静まってから執筆する作家もいる。その日常は様々だ。
ただ,概ね決まった気分転換の習慣を持っており,散歩が最も多く,水泳とかランニングとかの運動が多い。
コーヒーや紅茶というカフェインの入った飲み物も多いが,今では違法な薬物でも手に入った時期の作家たちは,覚せい剤や睡眠薬をよく使ったようだ。それで身を持ち崩すようなことはなく,創作の際の補助手段と考えていたようだ。
サルトルは,コリドランというアンフェタミンとアスピリンの混合薬を,規定は一日1,2錠のところを毎日20錠のんだ。一錠ごとに1,2ページ書いたという。
多少知っている人たちで気になったことのメモ。
フェデリコ・フェリーニ
一度に3時間以上は眠れないと言っていた。
イングマール・ベルイマン
晩年、寝つきが悪くなり、4〜5時間しか眠れなくなったため、やがて映画製作から引退した。
カール・マルクス
金銭の管理能力が無く、「金についての本を書いた者で、こんなに金のない者は、今までいなかったと思う。」と本人が書いている。悪筆だったことは有名で,そのために就職もできず,一生,エンゲルス等他人の援助に頼っていた。この本にはないが,マルクスの字は誰も読めないので,すべて夫人が清書したという。
カール・ユング
簡素な暮らしが好きで、灯油ランプとマッチ以外は、16世紀の様な家で過ごした。週末には、電気も水道もない家で、キャンプの様に自ら料理を作った。
イマニュエル・カント
規則正しい生活を送ったことで知られるが、40歳を過ぎてから、この習慣を自分に課したそうだ。虚弱だったので健康上の理由もあり、「ある種の画一性」を,習慣から道徳的な規範に変えようとした。そのため,起床、昼食、散歩、就寝の時刻は時計代わりになるほどだった。パイプで吸う刻みタバコも一服と決めていたが、そのパイプは年々大きくなったそうだ。ここもカントらしく,結構笑える。
ジェイムズ・ジョイス
自分で「モラルに欠け,浪費癖と飲酒癖のある男」と言っている。テノールの声が自慢で,酒場ではアイルランド民謡を大声で歌ったという。借金まみれだった。
エリック・サティ
パリから10kmほど離れたアルクイユに移住してからは,毎日,パリまで歩いて通った,ということは聞いていたが,服装も毎日同じだったそうだ。それは引っ越した年にささやかな遺産を相続したそうで,それで栗色のビリード地のスーツと山高帽を一ダースずつ買ったからだそうだ。食通で大食漢だった。淡々とした(と私は感じる)サティの音楽は毎日同じ道を歩いたことによるのではないかとある。
ショスタコーヴィチ
作曲するときはピアノで弾いてみることはなく,いきなり楽譜を書き上げたそうだ。仕事をしているところを,人に見せたことはないという。一気に書き上げるところはモーツァルトに似ている。既に全部頭の中にあって,それを書き留めるだけなのだそうだ。
アガサ・クリスティー
書斎を持たず,家事の合間に食卓や寝室の洗面化粧台にタイプライターを置いて執筆した。執筆の様子を写真にしたいという記者は,絵になる書斎がないので困ったという。
トルーマン・カポーティ
数字の合計にこだわっていて、電話番号やホテルの部屋番号の合計が不吉な数字だと、予定を取り止めた。
フランク・ロイド・ライト
仕事をしているところを滅多に人に見せなかった。有名な落水荘の設計では,クライアントの到着2時間前に描いた。仕事も精力的だったが,三番目の妻の回想ではライトは85歳でも1日に2-3回セックスが出来るほどだった。
グレン・グールド
趣味は無く、生活と仕事が一緒というのを自分でも異常だと思っていた。電話魔で相手の事は考えなかった。ピアノの練習は1日わずか1時間程度だった。
シューベルト
作曲は午前中だけ集中して行っていたが作曲以外の仕事は全く役立たずで、いつも知人に金を借りるという生活だった。
リスト
酒とタバコの毎日で、睡眠時間は短かった。
バックミンスター・フラー
睡眠時間を減らせれば仕事をする時間が増えると考え,「高頻度睡眠」を提唱した。6時間ごとに30分眠るというものだ。「集中力の崩壊」という兆候が起きたらすぐに眠るようにする。この実験を一年間行ったが,妻からは不評で止めざるを得なかった。この実験につきあった学生によれば,フラーは30秒で眠りに落ち,まるでスイッチを切るようだったと述べた。
ジャクソン・ポロック
画家仲間だった妻に勧められてニューヨークからロングアイランド東部の漁村に移り住んだ。飲み仲間との夜毎の深酒を止めさせるためだった。生活が改まり,この時期にドリップペィンティングの技法を開発している。1日12時間も寝た。
アイザックアシモフ
アシモフはブルックリンで菓子屋を営んでいた父親をよく手伝っていたのだそうだ。興味深いのでそっくり引用する。(iPadのSiriで口述筆記させたけど,文脈を理解しているわけではないようで,誤変換が結構多い)
「私は長時間働くのが好きだったのだと思う。なぜなら、後の人生で、「子供の頃から青年期まで働きづめだったから、今はのんびり昼まで寝ていよう」と思った事は一度もないからだ。
それどころか、私はあの菓子屋時代の労働習慣をずっと守ってきた。朝は5時に起きて、できるだけ早く仕事を始め、できるだけ長く働く。これを毎日、休日も続ける。自分から進んで休暇をとることもないし、休暇中でも仕事をしようとする(入院している時でされそうだ)。
要するに、私は現在も、これからも、ずっと菓子屋にいるのだ。もちろん、客の応対をしているわけではないし、金を受け取って釣り銭を渡しているわけでもない。やってくる人みんなに愛想良くしなければならないわけでもない(実はそれは昔からずっと苦手だった)。自分が本当にやりたいことをやっているのだ----しかしそこに当時と同じスケジュールがある。それは体に刷り込まれたものだ。それについて人はこう思うかもしれない。あんただってチャンスがあれば、それに逆らっていただろう、と。
確かに言えるのは、あの菓子屋は、私に様々なメリットを与えてくれた、と言うことだ。それは単なる生きるための手段では決してなく、圧倒的な幸福につながるものだった。それが長時間労働ととても強く結びついていたために、長く働くことが私にとって快感になり、生涯の賢い週間となったのだ。」
---以上
原題「DAILY RITUALS:How Artists Work」
フィルムアート社 (2014/12/15)
近・現代の作家、芸術家,音楽家,思想家,医師,科学者などの日常、1日の過ごし方を調べたもので,原題にもある通り,天才だけを取り上げたものではない。
これらの人たちは,創作することを苦悩とする場合もあり,楽しんでいる人もいる。午前中から午後にかけて集中して著述に励む人と,深夜という人も多い。普段は普通の主婦で,家人が寝静まってから執筆する作家もいる。その日常は様々だ。
ただ,概ね決まった気分転換の習慣を持っており,散歩が最も多く,水泳とかランニングとかの運動が多い。
コーヒーや紅茶というカフェインの入った飲み物も多いが,今では違法な薬物でも手に入った時期の作家たちは,覚せい剤や睡眠薬をよく使ったようだ。それで身を持ち崩すようなことはなく,創作の際の補助手段と考えていたようだ。
サルトルは,コリドランというアンフェタミンとアスピリンの混合薬を,規定は一日1,2錠のところを毎日20錠のんだ。一錠ごとに1,2ページ書いたという。
多少知っている人たちで気になったことのメモ。
フェデリコ・フェリーニ
一度に3時間以上は眠れないと言っていた。
イングマール・ベルイマン
晩年、寝つきが悪くなり、4〜5時間しか眠れなくなったため、やがて映画製作から引退した。
カール・マルクス
金銭の管理能力が無く、「金についての本を書いた者で、こんなに金のない者は、今までいなかったと思う。」と本人が書いている。悪筆だったことは有名で,そのために就職もできず,一生,エンゲルス等他人の援助に頼っていた。この本にはないが,マルクスの字は誰も読めないので,すべて夫人が清書したという。
カール・ユング
簡素な暮らしが好きで、灯油ランプとマッチ以外は、16世紀の様な家で過ごした。週末には、電気も水道もない家で、キャンプの様に自ら料理を作った。
イマニュエル・カント
規則正しい生活を送ったことで知られるが、40歳を過ぎてから、この習慣を自分に課したそうだ。虚弱だったので健康上の理由もあり、「ある種の画一性」を,習慣から道徳的な規範に変えようとした。そのため,起床、昼食、散歩、就寝の時刻は時計代わりになるほどだった。パイプで吸う刻みタバコも一服と決めていたが、そのパイプは年々大きくなったそうだ。ここもカントらしく,結構笑える。
ジェイムズ・ジョイス
自分で「モラルに欠け,浪費癖と飲酒癖のある男」と言っている。テノールの声が自慢で,酒場ではアイルランド民謡を大声で歌ったという。借金まみれだった。
エリック・サティ
パリから10kmほど離れたアルクイユに移住してからは,毎日,パリまで歩いて通った,ということは聞いていたが,服装も毎日同じだったそうだ。それは引っ越した年にささやかな遺産を相続したそうで,それで栗色のビリード地のスーツと山高帽を一ダースずつ買ったからだそうだ。食通で大食漢だった。淡々とした(と私は感じる)サティの音楽は毎日同じ道を歩いたことによるのではないかとある。
ショスタコーヴィチ
作曲するときはピアノで弾いてみることはなく,いきなり楽譜を書き上げたそうだ。仕事をしているところを,人に見せたことはないという。一気に書き上げるところはモーツァルトに似ている。既に全部頭の中にあって,それを書き留めるだけなのだそうだ。
アガサ・クリスティー
書斎を持たず,家事の合間に食卓や寝室の洗面化粧台にタイプライターを置いて執筆した。執筆の様子を写真にしたいという記者は,絵になる書斎がないので困ったという。
トルーマン・カポーティ
数字の合計にこだわっていて、電話番号やホテルの部屋番号の合計が不吉な数字だと、予定を取り止めた。
フランク・ロイド・ライト
仕事をしているところを滅多に人に見せなかった。有名な落水荘の設計では,クライアントの到着2時間前に描いた。仕事も精力的だったが,三番目の妻の回想ではライトは85歳でも1日に2-3回セックスが出来るほどだった。
グレン・グールド
趣味は無く、生活と仕事が一緒というのを自分でも異常だと思っていた。電話魔で相手の事は考えなかった。ピアノの練習は1日わずか1時間程度だった。
シューベルト
作曲は午前中だけ集中して行っていたが作曲以外の仕事は全く役立たずで、いつも知人に金を借りるという生活だった。
リスト
酒とタバコの毎日で、睡眠時間は短かった。
バックミンスター・フラー
睡眠時間を減らせれば仕事をする時間が増えると考え,「高頻度睡眠」を提唱した。6時間ごとに30分眠るというものだ。「集中力の崩壊」という兆候が起きたらすぐに眠るようにする。この実験を一年間行ったが,妻からは不評で止めざるを得なかった。この実験につきあった学生によれば,フラーは30秒で眠りに落ち,まるでスイッチを切るようだったと述べた。
ジャクソン・ポロック
画家仲間だった妻に勧められてニューヨークからロングアイランド東部の漁村に移り住んだ。飲み仲間との夜毎の深酒を止めさせるためだった。生活が改まり,この時期にドリップペィンティングの技法を開発している。1日12時間も寝た。
アイザックアシモフ
アシモフはブルックリンで菓子屋を営んでいた父親をよく手伝っていたのだそうだ。興味深いのでそっくり引用する。(iPadのSiriで口述筆記させたけど,文脈を理解しているわけではないようで,誤変換が結構多い)
「私は長時間働くのが好きだったのだと思う。なぜなら、後の人生で、「子供の頃から青年期まで働きづめだったから、今はのんびり昼まで寝ていよう」と思った事は一度もないからだ。
それどころか、私はあの菓子屋時代の労働習慣をずっと守ってきた。朝は5時に起きて、できるだけ早く仕事を始め、できるだけ長く働く。これを毎日、休日も続ける。自分から進んで休暇をとることもないし、休暇中でも仕事をしようとする(入院している時でされそうだ)。
要するに、私は現在も、これからも、ずっと菓子屋にいるのだ。もちろん、客の応対をしているわけではないし、金を受け取って釣り銭を渡しているわけでもない。やってくる人みんなに愛想良くしなければならないわけでもない(実はそれは昔からずっと苦手だった)。自分が本当にやりたいことをやっているのだ----しかしそこに当時と同じスケジュールがある。それは体に刷り込まれたものだ。それについて人はこう思うかもしれない。あんただってチャンスがあれば、それに逆らっていただろう、と。
確かに言えるのは、あの菓子屋は、私に様々なメリットを与えてくれた、と言うことだ。それは単なる生きるための手段では決してなく、圧倒的な幸福につながるものだった。それが長時間労働ととても強く結びついていたために、長く働くことが私にとって快感になり、生涯の賢い週間となったのだ。」
---以上

最近のコメント